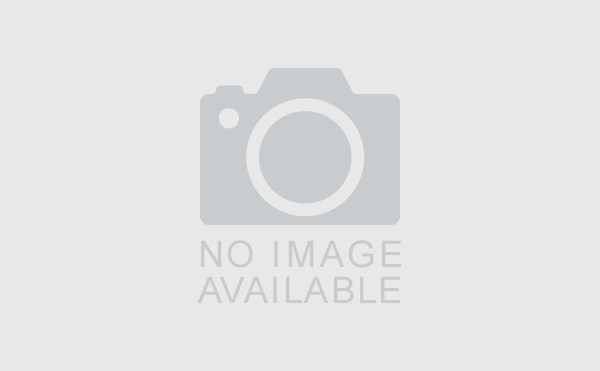2025年8月23日(土)オンライン講演会
8月23日(土)、オンラインにて公開講演会が開催されました。盛永審一郎教授の演題は『「生きる権利」と「死ぬ権利」』、95名の方がご参加くださいました。
アンケートから抜粋し、参加者の声をご紹介します。
【アンケート内容】
- 私には難しい内容でしたが、人権と安楽死に関して大変勉強になりました。
- それぞれの国での基本的な考え方をわかりやすく説明してくださり、理解しやすい順序での構成になっていたので、難しい内容ではありましたが理解することができました。
- 生と死をあらためて考える良い機会となりました。ありがとうございました。
- 様々な国の「生きる権利」と「死ぬ権利」について学ぶことができました。ありがとうございます。
- 各国によって尊厳死の考え方が違う事が良く分かりました。ありがとうございました。
今後も尊厳死について勉強していきたいです。 - 欧州とアメリカ合州国との考え方に違いがあるとは知りませんでした。
- 今現在、修士課程にて修士論文に死ぬ権利をテーマとして執筆中です。非常に参考になりました。ありがとうございました。
- 正直に申しますと、とても難しい内容でした。わかりにくかったというより、私の理解が追いついていかなかった、という表現が正しいと思います。ただ、文化の違いによって考え方が異なることがあるのだと、改めて知りました。また、オランダの安楽死実績で徐々に数が増えていくことは高齢化が進む状況で当然のこと、カップルの安楽死は高齢夫婦の選択であろうこと、決して安楽死法があると、滑り落ちるように増えるわけではないということに言及いただき理解を深めることができました。ありがとうございました。
- 盛永先生のお考えを詳しくお聞きする良い機会でした。ありがとうございました。
- 「自己決定権」について分かり易いお話でした。
- 国によってかなり違う考え方があるということがわかりました。
- スペインは安楽死法で安楽死が認められているけれど、死刑は認められていないというところが、日本と真逆で、国民性の違い等を表しているのなかと思いました。
安楽死等についてしっかりと考えるきっかけになりました。 - 人類の、一員として有るべき姿が見えて来ました。71歳の身としては、他人事ではありません。会員参加を真剣に考えます。ありがとうございました。
- 自分がまだ真剣に尊厳死や死の情報を集めて考えたことがないので、分かりにくいという表現になりましたが、内容自体が意味があるものだという本質的な感覚があり参加してよかったです。
- 多くの要素をもつ、重要だがむずかしい問題で、いつ聞いても、何度聞いても考えさせられることです。
- 大変勉強になりました。看護師として患者の権利を深く考えることをしていけたらと思っています。
- 尊厳死と安楽死はまったく別モノと考えていたがそんなに単純なものではないと思った。
- とても、難しい内容でした。安楽死は、本人の強い意志でしょうが、日本では、医師や家族が、賛同するか、難しい。生きる事、死ぬ事、大きな題材でした。ありがとうございました。
- 簡単に、(そしてたぶん永遠に)結論は出ないだろうと感じました。
- 講演ありがとうございます。理解を深める機会をいただき感謝申し上げます。
大変に大切なテーマであると思いますが講演の内容が専門的で理解が十分できないところもありました。もう少し一般市民向けで内容を咀嚼したご説明の機会もあれば有難く思います。 - 大変勉強になりました。いつも貴重な機会をありがとうございます!
- 国際間でも死に対する考え方、とらえ方が全く違うことに驚きました。難しい問題だとあらためて感じました。
- 現在、大学院で死の自己決定をテーマにした研究を行っています。盛永先生は法律の観点から死を権利として研究されておられますので、臨床現場で死の自己決定を望む患者の意思の尊重という観点から研究している私にとって、とても勉強になりました。
- 安楽死と尊厳死の違いがなんとなくわかった。又日本とアメリカ、欧米諸国の考え方に違いがあることは新発見だった。現在の私は協会の考え方に共感しています。
- 生きる権利の中に死ぬ権利が含まれているという言葉が印象的でした。
ひとり一人が最期までどう生ききるか、子どもの時から考える機会を提供していくことが必要だと考えています - いびつな人口構成(少子高齢化)で社会保障制度崩壊の危機に直面している日本では、特に尊厳死の制度化は必要かつ賛成です。どのような歯止めをかけるかとか、利害関係の問題などもあり、わが国では時間がかかるのが自分なりに理解できました。
- 医療現場で働いている看護師です。自律の意味について改めて考える機会となりました。共通の認識の齟齬は同じ日本人でもあるわけで、西洋などの文化の違いも加味して、日本ではどう考えていくか、法にすると決定となってしまいますが、考えていくということ自体が大切なことだと思います。人口動態上、高齢者が増える、意思決定の面でも大きな課題となっている現状で、医療界だけではなく、国として考えていく必要があると思いました。貴重な講演ありがとうございました。
- 認知症と尊厳死を、どう考えれば良いのでしょう?明治生まれだった祖父母は認知症にならず、70半ばで亡くなりました。今振り返ると、家族にとって有難かった死だったと感じています。高齢者施設の長期入居は経済的にも精神的にも大変だからです。戦後生まれの私が認知症になったら、受給されている年金では入居不可能です。認知症患者の安楽死にも目を向ける社会になって欲しいと願っています。
- 長年生きる権利は死ぬ権利と同じだと考えていましたが、学問的な裏付けや経緯をまとめて下さり、何が議論されて今日に至るのかよくわかり、たいへん有益なお話でした。
自分の専門(哲学)と直結したお話だったので、会員として自分の終末期を自己決定したいと思っている個人の立場からの視点と、哲学研究者としての視点の2つを常に照らしながら聴講しました。 - 学術的根拠がよく整理されていてわかりやすかった。
- オランダ等での議論の背景や制度的な側面についても理解することができ、たいへん有意義でした。ありがとうございました。
- 今回のご講義を聴講し、医療の臨床での様々な場面での自由意思決定と自己決定の双方の視点について改めて、勉強する機会となりました。ありがとうございました。
- 難しい議論でしたが大変勉強になりました。有難うございました。
- 人権のなかでも、バルセロナ宣言にもある「integrity」に重点をおく考え方が興味深いです。
- 書籍で勉強するには時間のかかる全体像やポイントを示してもらい、ありがたく思いました。
- 非常に難しいテーマでしたが、同時に非常に興味深く、1時間50分があっという間でした。
- 前半の法律を読み解くのが難しいと感じました。海外の事例について、もう少し多く知りたかったです。また、日本における尊厳死が適用されなかった事例についても死ぬ権利に関わる事なので、教えていただきたかったです。
- 難しかった。世界の状況が垣間見えたが、もっと、各国の実情が知りたいと思った。
- <生命の神聖さの原則>と<死ぬ権利>が矛盾しないということについて、ECtHRに基づいてご説明頂き有難うございました。根拠がよく分かりました。さらに、島薗先生の記事と関連付けてご説明頂き、さらに理解が深まりました。また、滑り坂論証についても詳しくご説明頂き有難うございました。死の自己決定はautonomyではなくpersonal autonomyが重視されていることがよく理解できました。ショーペンハウアーについて触れて頂いた部分も興味深かったです。時間があればもっと詳しくお聞きしたかったです。
- 生命に関することをより深く考えることができる内容でした。大変難しいことを優しくお教えいただけたと思います。ありがとうございました。
- 英米の生命倫理に偏らないお話が聞けました。
- センセーショナルに取り上げられがちな積極的安楽死を法制化した各国の実際について丁寧に取り上げて下さり、大変勉強になりました。
以上