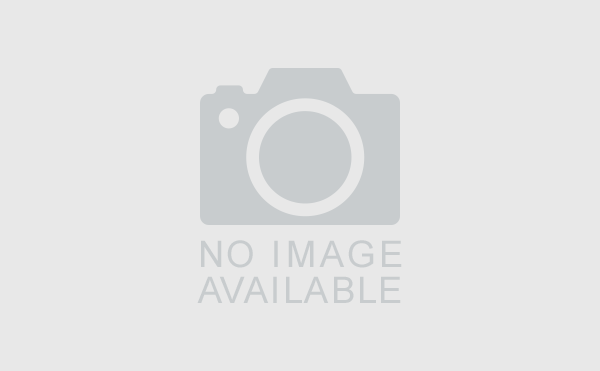東北支部リレーエッセイ「LW(リビング・ウィル)のチカラ」 (26)
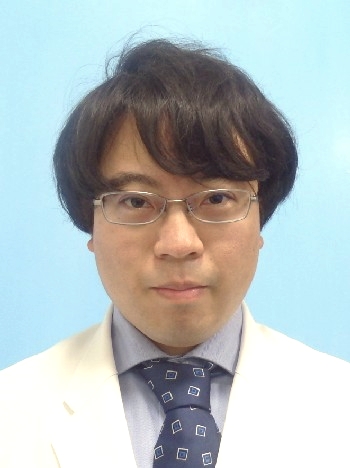
「日本人に合った先々の話し合いって何だろう?」
竹田綜合病院 緩和医療科 平塚裕介
私は緩和ケア医かつ臨床研究医として、臨床現場で生じた疑問を解決するための研究に取り組んできました。最初は、患者さんやご家族からの「いつまで生きられるのか?」という問いに答えるために始めた研究が徐々に発展し、現在は「どのような対話を重ねることで、できるだけ心残りの少ない人生になるか」という壮大なテーマに取り組んでいます。
研究テーマにも関連して、『アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)』について考えることは多いです。しかし、もしものときに備えて話し合うことはそう簡単ではないと年々懐疑的になっています。自分の両親に実行(1回目)してみましたが、「縁起でもない」「考えたくもない」で終わりました。代理意思決定者は私ということで異論はなかったのですが・・・。しかし2回目では、今度は父親が自分の思いを話してくれて、どのように過ごしたいかの希望が明確になりました。
なぜ2回目は話し合いが進んだのかというと、実は1回目と2回目の間に、父の姉(私の叔母)が亡くなったのです。その際に、どのように過ごすか、葬儀やお墓をどうするかも何も決めておらず、大変だったのをみて、「自分の場合は・・・」と思ったようでした。父にとっては「人生の終わり」がどこか遠くの話だったのが、一気に現実味を帯びたのでしょう。一方で、母は1回目から何も進展はありませんでした。
「もしものときに」と言っても、身内での不幸があったり、自身が病に罹らないと、現実味をもって話し合いはできないと考えています。一方で、最期については(話題にはしにくいですが)、「自然のままに」など希望をもっている方は多いと思います。遠い未来ではなく、「少し先(1-2か月後)の未来」についての話し合いを繰り返しながら、理想の最期が迎えるように支援するのが、日本人に合った人生会議なのだろうと思いつつ、日々の診療に取り組んでいます。

韓国での講演後の1枚。先々の話し合いは韓国でも重要課題でした。

台湾での講演後の表彰時の1枚。台湾では緩和ケアは国策でも最重要課題のようです。