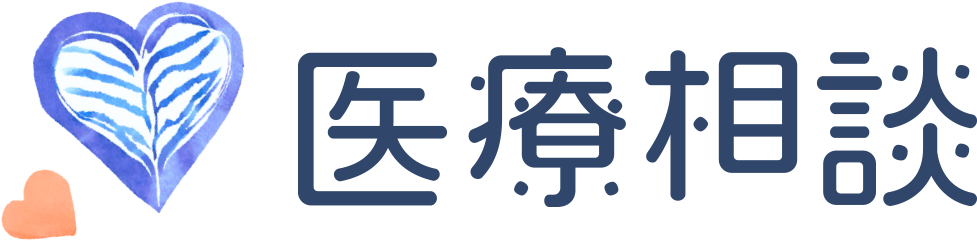85歳の母親は、要介護4で自宅で訪問医療を受けていました。
1週間前、食事中に食べ物を喉に詰まらせて救急車を呼びました。その場で医師から人工呼吸器をつけるとかどうか問われ、咄嗟のことでしたので、つけることを承諾してしまいました。しかし、意識は戻らず数日前に医師から、これからも意識はもどることはなく脳は植物状態といわれました。そして、長く喉に管を入れておくことはできないので、喉に穴を開ける気管切開を勧められましたが迷っています。
母のリビング・ウイルと希望表明書を医師に渡して中止をお願いしましたが、倫理上、人工呼吸器は外せないといいます。母は早くから尊厳死協会に加入し延命治療は望んでいませんでしたが、一度付けた人工呼吸器は外すことはできないのでしょうか。
咄嗟の時のことを考えて家族間で心づもりをしていても、いざとなったらその通りに判断できるかは難しいものです。
人工呼吸器は命を救うために必要な装置になりますが、お母様のように意識が戻ることのない植物状態(遷延性意識障害)になると、死の瞬間を引き延ばすためだけの延命措置になりかねません。
しかし、今は人工呼吸器をつけて命を支えられていますので、法的に認められていない現状では、はずす行為が犯罪に問われかねないという病院側の危惧も否めません。
気管内に挿入されている管は長期間入れていると気管粘膜が障害され、潰瘍や狭窄を起こしたり、感染の原因となります。そのため、気管挿管から2〜3週間経過すると、主治医から気管切開を勧められるのが一般的です。気管切開は自分で呼吸が十分にできるようになると閉じることはできますが、意識が戻らず自力で痰を出すことができなければ難しくなります。
現在、日本に於いての終末期医療の法的整備はなく、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」や、各医学会から出されているガイドラインに、本人の意思が確認できれば、緩和ケアが十分に行われた上で、医療・ケア行為の中止はあり得ると記載されています。しかし、これらのガイドラインが一般に普及しているといえないのが実情です。
お母様は尊厳死協会に入会し事前にLW(リビングウイル)や希望表明書を作成して、家族とは十分な話し合いを持ち、人生の最終段階になった時は延命治療はしないことを共有しています。本人の意思を尊重するためには、医療従事者と話し合うACPをお勧めします。ACPはアドバンス・ケア・プランニングの略で、人生会議という愛称で呼ばれています。厚生労働省が人生の最終段階における医療体制整備事業として推し進めているもので、患者・家族・医療従事者の話し合いを通じて、患者の価値観を明らかにし、これからの治療・ケアを明確にするプロセスのことです。
本人が何を大切にして生き、最後をどのように迎えたいかを家族と医療従事者が対話を繰り返し、共有意思決定を行うことが大切です。
外部委員会を含めた臨床倫理委員会の場で検討をお願いしてもよいと思います。
そして何よりも、意識がなくご自分の意思を明確にできないお母様に代わり、ご家族が代諾者となる苦悩は計り知れないものとお察しいたします。しかし、元気な時から人生の最終段階は、延命治療はをしないで自然で安らかに迎えたいとするお母様の願いである、LWと希望表明書を尊重してほしいものです。
豆知識
臨床倫理委員会とは
医療や介護の現場において、直面する治療法とケアおよび療養場所等の選択に関わる諸問題をはじめ倫理的な判断が難しい状況において、解決策を提示し、助言を行うことを目的としています。構成員は医師、看護師、ケースワーカーなどさまざまな専門職から成り立ち、複数の選択肢からいずれの方法を選択すべきか、情報を整理・分析し、本人にとって現実的な最善の選択肢をめぐって、本人・家族側と医療・ケアチーム側がコミュニケーションを重ね合意を形成します。