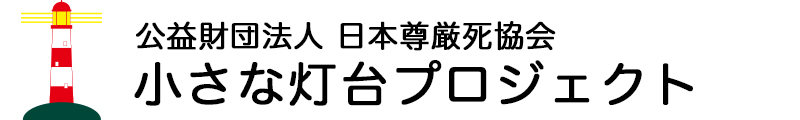【情報BOX】家族と契約 No.3 死後のことを託す―遺言・死後事務委任契約・死因贈与契約
ここまで、本人の(生前の)「判断能力」等をサポートするのが「後見制度」や見守り契約などの各種委任契約だという話をしてきましたが、これらは当然ながら本人が存命中の課題と対処法です。では、本人の「死後」に必要な手続きについてはどう決めればよいでしょうか? これはご存じだと思いますが主に「遺言」によって決めておくことができます。
◎本人の「死後」のことは遺言で決められる
「遺言」は「単独行為」といって、厳密には「契約」とは異なる行為です。本人が自分ひとりで一方的にその内容を決められるからです(契約のように相手方との合意がありません)。ただ、目的は契約とよく似ていて、「遺言」すれば本人は自分の財産を誰にどれくらい譲るのかを(本人の意思で、ほぼ自由に)決めることができます。ただし本人が意思表示したから絶対にその通りになるかというと、意思表示することとそれが実現することとは厳密には別のことなので、その点は冷静にとらえたいところです。
「遺言」をしない方も、世の中には大勢います。よくちまたでは「財産が少なくてももめることはある」とか「相続を争族にしてはならない」などと、遺言を強く勧める風潮がありますが、遺言にメリットがあるかどうかは個人が主体的に考えるべきです。「遺言」にも限界はありますから、過度に期待せず、むしろ一長一短があることは知っておくべきだと思います。
◎遺言はすべきなのか?
逆に「遺言」がない場合はどうなるかというと、本人の死後に「相続人」が民法に従って相続(法定相続といいます)の手続きをしなければなりません。これには「遺産分割協議」という、相続人同士の「会議」による、全員の同意が必要になります。「全員の同意」というところが大変なところです。つまり、なかなかまとまらなかったり、意見が合わずにもめたりすることがあります。よって、相続人が多い場合は「遺言」があった方がよい、と言われるのは、こうした会議をしなくても「遺言書」どおりに手続きができるからです。それはその通りですが、とはいえその「遺言書」の内容に不満がある相続人がいれば、結局はもめるに違いありません。
要するに「遺言」をするべきかどうかは、その「目的」によります。あらかじめ相続人の都合を聞いてそれに沿った内容にする(相続人にとっては結論が同じなら、遺言により手続きがスムーズになる)とか、あるいはご本人にとって「遺言」した方が「自分の心が落ち着く」などの明確な目的があればした方がよく、確たる目的が見当たらないときはしなくてもよいものだと思います。ただ、ひとつはっきりといえることは、もし作るのであれば早い方が良いということです。遺言は判断しなければならないことが多いですし、そもそも資産の棚卸(たなおろし)はかなり面倒で、かつ正確でなければいけませんから、結構エネルギーが要ります。作らなくてよいなら忘れる、作るなら元気なうち、がお勧めです。
◎死後事務委任契約とは?
前回、任意後見契約には範囲外の事務があるといいましたが、「遺言」にも範囲はあります。「遺言」は、主に、本人の財産(遺産)を死後にどうするか(誰に何をどれだけあげるのか)を決めておくためのものです。より詳しく言えば、遺言書に記載することによって法的効力が認められる事項は、法律で明確に決まっています。これを「遺言事項」といいます。もし遺言書に「遺言事項ではないこと」を書いても、遺言としては有効になりません。書いても無効です。そこで「遺言事項」にはどんなものがあるのかを、具体的に見ていきましょう。
▼遺言事項の例
| ・推定相続人の廃除(民法893)と取消(民法894) ・相続分の指定(民法902) ・遺産分割方法の指定及び分割の禁止(民法908) ・遺産分割の際の担保責任に関する別段の意思表示(民法914) ・包括遺贈及び特定遺贈(民法964) ・以下の事項についての「別段の定め」 【受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄(民法988)/受遺者の死亡による遺贈の失効(民法994)/受遺者による果実の取得(民法992)/遺贈の無効又は失効の場合における目的財産の帰属(民法995)/相続財産に属しない権利の遺贈における遺贈義務者の責任(民法997②)/受遺者の負担付遺贈の放棄(民法1002②)/負担付遺贈の受遺者の免責(民法1003)】 ・遺言執行者の指定(民法1006①) ・以下の事項についての「別段の定め」 【特定財産に関する遺言の失効(民法1014④)/遺言執行者の復任権(民法1016①)/遺言執行者が数人ある場合の任務の失効(民法1017)/遺言執行者の報酬(民法1018)】 ・遺言の撤回(民法1022) ・複数受遺者又は受贈者の負担額に関する別段の定め(民法1047条①二) ・遺言認知(民法781②/戸64) ・未成年後見人の指定(民法839) ・未成年後見監督人の指定(民法848) ・祭祀主催者の指定(民法897) ・特別受益の持戻しの免除(民法903③) ・一般財団法人設立(一般社団・財団152) ・信託の設定(信託3) ・保険金受取人の変更(保険44①/73①) |
いかがでしょうか。「遺言事項」はたくさんあるように見えて、要するに「相続」に関することや「身分関係」のことがほとんどですよね。それぞれ重要な事ですが、亡くなった方の各種公共料金の精算や、葬儀、埋葬に関することは含まれていません。つまり葬儀などのいわゆる身辺整理や遺品整理に関することは「遺言事項ではない」ため遺言に書くことはできません(「付言」といって、法的効力はないことを承知の上で、遺言書に書くこと自体は可能です)。こうしたことはご家族がやれば済むことではありますが、ご家族がいらっしゃらないとか、疎遠になっている方などには死後の事務を頼んでおきたいニーズもあります。そこで、残っている債務の支払や、葬儀の主宰、埋葬、供養、片付け、相続財産管理人の選任の申立てなどの事務を依頼することを「死後事務委任契約」といいます。
◎死後事務委任契約は、なぜ有効?
そもそも、生前に死後の事務を委任する契約は、有効なのでしょうか? まず「委任契約」は民法の規定により、委任者又は受任者が死亡すると終了します(民法第653条)。先ほど紹介した「任意後見契約」も「一種の委任契約」ですから、本人の死亡により終了することになります。ゆえに、本人の死後に契約上の事務をすることはできません。ただし民法653条の規定は「強行規定ではない」と考えられている(=契約で別の定めをすることもできるとされている)ため、特約で本人の死後の事務を目的とする委任契約をすることが可能です。よって実務上は、本人が「死後の事務の処理」を誰かに頼みたい人と「死後事務委任契約」を締結すれば(民法第653条の規定にかかわらず)、本人(委任者)の死亡によっても委任終了はせず、有効に対処できるのです。
とはいえ、委任者が死亡した後に行われる事務についての契約なので、その内容は慎重かつ具体的に決めるべきです。たとえばあまりにも実現が難しすぎたり、曖昧だったりする内容や、あるいは「遺言と異なる内容の定め」は受任者を困惑させ、結果的に履行できないことになりかねません。さらにもうひとつ、死後に効力を発揮する契約の例としては、「死因贈与契約」という契約があります。
◎死因贈与契約とは?
「死因贈与」とは文字通り、本人の「死後に」財産を「贈与する」契約です。つまり「死んだらこの財産をあげます(贈与します)」という約束ですが、亡くなった後に特定の人に財産が渡る、ということでは「死因贈与契約」も「遺言」も同じ効果があります。では「死因贈与」と「遺言」はどう違うのでしょうか? 自分の意思だけで決められる(単独行為である)「遺言」と違って、死因贈与契約は「契約」ですから、当然、相手方(財産をもらう人=受贈者)との合意が必要です。つまり双方向のやり取りとなり、お互いの合意を確認して行うところが「遺言」とは違います。絶対ではありませんが、死因贈与契約の方が、「遺言」よりも履行が確実な感覚はあります(ただし契約も、撤回の可能性は残ります)。
▼条件付きで財産をあげることも“契約”できる
ところで「死因贈与契約」には、ある種の「交換条件」を付けることもできます。たとえば「“介護をしてくれたら” 死因贈与します」みたいな内容で契約することができることになり、これは「“負担付”死因贈与契約」とよばれています。受贈者が負担を履行していれば、原則として解除できない契約とされていて、確実性の高い贈与の方法といえそうです。
こういうことは「遺言」ではできないのか? といえば、似た効果を生むものとして、同居や介護をしてもらう相続人に有利な遺言を遺して、それを生前から伝えておくことで「負担付死因贈与」に近い状況になります。あるいは「負担付遺贈」といって、「遺言」によって一定の債務とひきかえに「遺贈」するという定めもできます。
⇒「家族と契約 No.4 まとめ&今注目の家族信託」に続く