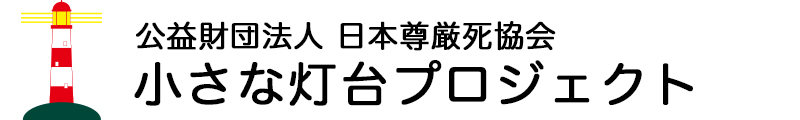私が長くボランティアをしていたなじみの緩和ケア病棟での希望の最期
遺族アンケート
82歳夫/看取った人・妻/東京都/2022年回答
入院した緩和ケア病棟には10年前から私(家族)がボランティアをしていて、最後にはそこで過ごせたらと話をしていた。日常生活でどのような形で生を全うできるかよく話し合っていたので、私も迷いがなく、本人には病状や入院のことなど伝えられた。コロナ禍でも本人の意思を必ず確かめ、治療検査入退院を行った。亡くなる2日前に「本当に家に帰って一緒に過ごしたいのだけれど、できなくてごめんね」と言うと、首を振って「ここがいい」とはっきり言った。主治医も看護部長もボランティアの時からの知り合いで、皆によくしていていただいてありがたいです。
協会からのコメント
欧米諸国の病院は、医療ボランティアの種類も人数も多いことでよく知られています。1980年代にカナダのトロント小児病院の医療ボランティアの実際を視察に行ったことがあります。そこのボランティアコーディネーターに、「感染対策や教育などのたくさんの困難があるにもかかわらず、ボランティアを受け入れる目的はなんですか?」と質問すると、「一般市民に人の生死・病気のありようを深く知り、理解してもらうには、病院職員と共に働くことが一番の教育効果があるから」と言われたことが強く印象に残っています。確かに現代の医療知識の変化、膨大な量……ネット社会でますます進むバーチャルな感覚だけでは、誰もが「病気や死」を自分事として消化しきれない現実があります。その溝を埋める手立てとして、医療ボランティアの受け入れは意味があると納得したものです。
10年もの長きにわたりボランティアをしてこられた緩和病棟は、ご家族にとっても、そこが「なじみの居場所」になっていたのでは? 人生体験型ボランティアを提案したくなるモデルにしたい「看取りのエピソード」です。