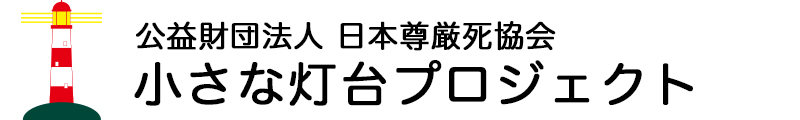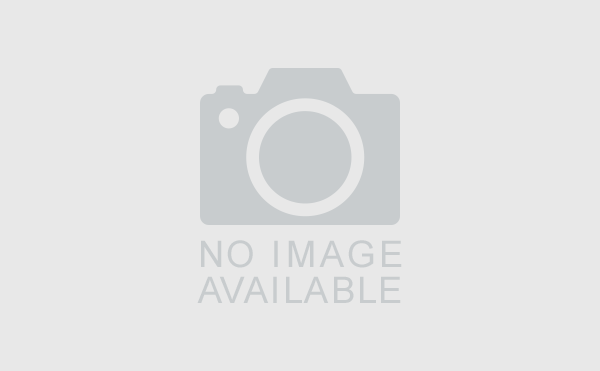「在宅看取り」を支えるサポート・システム 語り合おう「ACP」
遺族アンケート
85歳夫/看取った人・妻/広島県/2023年回答
大腸がんによる人工肛門の主人を、3年3か月老々介護。同居の息子家族、介護支援の人たち、往診の先生等、周囲の援助がなかったら自宅で看取ることはできなかったです。
また、本人の尊厳死の意志が大変強く、尊厳死協会に入っていて良かったと、皆様に感謝して過ごしています。
協会からのコメント
「本人の尊厳死の意志が大変強く、尊厳死協会に入っていて良かった」と言われるように、その意思が「形」として見せられるほど明確で、さらに、老々介護をサポートしてくれる同居の家族、そして介護支援の人たち(ケアマネジャー・ホームヘルパー・訪問看護師・訪問医師・訪問歯科医師・訪問薬剤師・福祉用具専門相談員・訪問理美容師の方々や配食サービス・訪問入浴サービスなどの事業者)の助けを、受け容れ、活用したからこそ実現できた見事な「在宅看取りのエピソード」です。
今、厚生労働省が中心になって推奨しているACP(アドバンス・ケア・プランニング)には、人生の最終段階での「医療やケアについて、どうしてほしいかの意思を明確にしてほしい」、そうしたら、その希望に沿えるように、地域包括ケアシステムという医療・ケア体制で「あなたと、介護するご家族を全力でサポートしますよ」という意味が含まれているのです。
ところが「介護は家族が担うもの。家に家族以外の他人に入ってもらいたくない」という既成概念にとらわれて「地域包括支援センター」という相談機関があるにもかかわらず、存在すら知らない人、利用しようとしない人々もまだまだ多いのが現状です。
特に「家で最期まで」と「在宅看取り」を希望される方々のために、今、急ピッチでそのサポート・サービスシステムの構築と普及活動が進められています。しかし、まだまだ十分ではありません。また、どのようなサービスを、いつ、どのように提供したら良いか? も模索中です。
介護福祉は、ご本人およびご家族が希望を申し出て、初めて機能します。企業の商品やサービスのように、希望もしないのに、営業の人が電話や訪問してきて、あれこれ勧めたり押し付けたりする類のものではないのです。
行政・関係医療福祉機関も、ケアサービスの種類が具体的にわかるように、地域での広報活動が不可欠とされ、あらゆる方法を駆使して情報発信されています。
まずは、地域にどのようなケアサービスがあり、それはどのように利用すれば良いのかを知ろうという関心をもちましょう。そして、この「看取りのエピソード」のように、地域包括ケアシステムを活用された方々が、今後、具体的な活用体験を投稿していただけるとうれしいです。各地域のサロン活動などを通して、もっともっとACPを、そして実際のケアサービス利用体験も語り合っていきましょう。