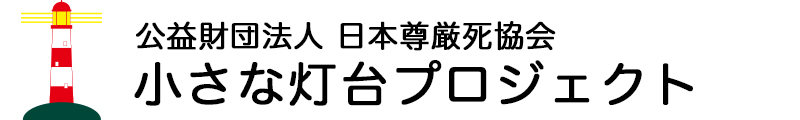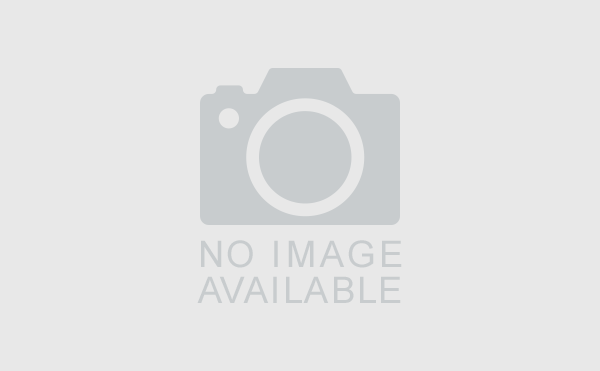【情報BOX】高齢者と死―考えてみませんか? 増える高齢者の「孤独死」「孤立死」そして「自死」―
「小さな灯台」は、人生の最期を幸福にとの想いで「尊厳ある最期」を遂げられたご家族の投稿をご紹介し続けています。「尊厳死」は、ご家族や地域のさまざまな専門職のサポートを得て、初めて可能になる「逝き方」であることがおわかりいただけるのではないでしょうか?
2023年度の投稿の中で一件、PSP(進行性核上性麻痺・指定難病5・享年78歳)という難病を苦に自死されたご遺族の方からの投稿がありました。「(前略)自分の力で死ねると思って生をたち切ったと思います。私が健康な体なら、もう少し一緒に暮らせたかなとすまない気持ちでいっぱいです(後略)」と。看取った奥様も乳がんと網膜色素変性症を患っておられ、老々介護の日々だったようです。そのようなつらい最期を予防できる方法はないものでしょうか?
また、死は誰にでも必ず訪れるものなのに、それに対するサポート体制は「超高齢・多死社会」を迎えた我が国の時代にマッチしているのでしょうか? という思いもあり、高齢者の死、特に今回は「孤独死」「孤立死」「自死」を【情報BOX】でとりあげてみることにしました。
◎統計で知ろう! 高齢者の「孤独死」「孤立死」「自死」の現状
1.「孤独死」「孤立死」の8割は高齢者
「警察で取り扱った死者(検死対象)約20万人のうち、一人暮らしの在宅死は4割近くの約7万6000人。年代別で、65歳以上の高齢者が8割近くをしめた(2025年4月警視庁発表)」というニュースが報道されました。「孤独死」「孤立死」について統計データが発表されたのは初めてです。ただし、そのうち4割近くが当日か翌日に発見されているため、その方たちは異変に気付いてくれる誰かとの交流があったと思われます。
※「孤独死」は、人との交流はあるけれど、急な体調変化などによって誰にも看取られずに亡くなること。「孤立死」は人との交流がない中で、誰にも看取られずに亡くなることです。統計上は死後8日以上経過して発見され、生前に社会的に孤立していたとみられる人を「孤立死した人」としています。
単身高齢者の中には「自分も誰にも看取られずに死ぬんじゃないか」と不安に思う人が多いのも頷けます。
2.日本での自殺者は年間約2万人―4人に1人は70歳以上
日本での自殺者のうち、70歳以上の割合は24.8%1)で約4人に1人は高齢者ということになります。70歳以上人口は総人口の23.4%1)であることを考えると、他の年齢階級に比べて突出して高齢者が多く自殺しているとはいえません。また、高齢者の自殺率は減少傾向ではありますが、それでも無視できない数であり、社会的課題といえます。
◎ 高齢者の自殺の特徴
1. 原因は複合的な要因の連鎖― 一番の危険因子は「うつ病」
自殺の原因はさまざまな要因が連鎖しているケースがほとんどで、それが「うつ病」の引き金となって自殺に至ることが知られています。そして高齢者の自殺の原因には、他の世代とは違う特徴があります。
▶健康問題
令和6年の統計では、高齢者の自殺の原因は「健康問題(83.6%)」「家庭問題(21.6%)」「経済・生活問題(12.0%)」1)と続き、病気(健康状態)が将来への不安、大きなストレスにつながっていることは間違いありません。特に高齢者は複数の病気、さらには完治しない慢性疾患を抱えていることが多く、健康状態に悲観的になりがちです。
※薬にも注意しましょう
見落とされがちですが、高齢者が複数の疾患を抱えているということは、薬を多く処方されている可能性があります。多くの薬を服用することで、うつ状態を引き起こす可能性もありますので注意が必要です。
【情報BOX】尊厳死を希望する人の代諾者になるあなたへ- 親の“老い”と向き合う時に役立つ《老い知識》のすすめ No.2薬は5種類までを参照
▶喪失・孤独・孤立
高齢者は晩年になってさまざまなものを失います。仕事や社会的地位を失い、家族や地域とのつながりを失い、世間からは「老害」などといわれて尊厳を失い、生きがいを失い……そのうちに「自分には生きる価値がない」と考えてしまいます。また、配偶者や友人など親しかった人の死を経験して孤独になる人も増えます。このような「喪失感」「孤独感」からうつ状態となり、自殺が増えることも後期高齢者の自殺の特徴です。
☞トピックス
日本の高齢者4.6万人を7年間追跡し、社会的つながりと自殺との関連を調べたところ、「孤食」の状態にある人は、自殺死亡のリスクが約2.8倍高かったという推計結果が発表されました2)。
2. 高齢者のうつ病は対応が遅れがち
このように「うつ病」のような精神疾患が自殺の背景にあることは知られていますが、下記のような理由から適切な治療を受けられず、高齢者のうつ病は対応が遅れる傾向があります。
- 人との関わりが減り、周囲の人が気付きにくい
- 「年のせい」と思われたり「認知症」と間違われたりしやすい
- 「うつ病」という言葉は、高齢者が若い頃には一般に知られていなかった病名なので、高齢者自身は「うつ病かもしれない」と気付きにくい
- 高齢者自身が医療機関を受診したがらない(世代的に精神科への抵抗が強い)
3. 人のサポートを受けたがらない高齢者
前述したように「孤独」が高齢者の心身の健康に及ぼす影響は大きいのですが、単純に一人暮らしの高齢者→孤独→自殺という構図ではありません。
実際、自殺した高齢者のうち同居人がいる人の割合の方が高いのです。同居する家族がいる場合には「家族に迷惑をかけている、家族の重荷になるくらいなら死んだ方が……」という思考に陥ることもあります。
症状に気付いても自分で治そうとする人が7割近く(住民団体「心と命を考える会」)、それは「子どもや家族に迷惑をかけたくない」、家族に限らず「人の迷惑になりたくない」という日本人に根強い考え方によるものだと思います。
せっかく地域包括ケアシステムという各種専門職のネットワークで、高齢者の病気を治療しながら不自由な暮らしをサポートする「丸ごと支援」しようとしていても、活用されなければ「机上の空論」になってしまいます。
◎高齢者の「孤独」「孤立」「自死」の予防対策は生きる支援
1. 高齢者を孤立させない周囲の工夫
単身高齢者はこれからも増え続けます。まずは地域社会とのつながりの中で高齢者を孤立させない工夫が必要です。さらに地域包括ケアシステムの中で、精神状態が不安定な高齢者を見つけ、医療につなげること12)13)……。我が国でも2006年自殺対策基本法を施行、2016年厚生労働省に自殺対策推進室を設置するなど対策を推進してきました。
各地域でも自治体や民間・住民団体がさまざまな取り組みをしていて、一定の成果は出ていると思います。事実、この10年で自殺者数は年間約3万人から約2万人にまで減少しています。
2. 新しいつながりが、新しい解決力を生む
超高齢社会では、老々介護・家族による介護が限界であることは医療福祉の関係者も十分理解しています。だからこそ「新しいつながりが、新しい解決力を生む(NPO法人自殺対策支援センターライフリンクのモットー)」に賛同します。高齢者自身が血縁・知人だけでなく、公的支援サービスやNPOなどの支援者を求めやすい風潮・生活環境をつくっていく必要があるように思います。
3. 生きる支援
しかし、一番大切なのは高齢者自身が「生きて何かを成したいと思えること、それを諦めさせないこと」です。
NPO法人自殺対策支援センターライフリンクでは、自殺対策を「生きる支援」ととらえていますが、この理念には大いに賛同します。私たちがやるべきことは「生きる支援」です。
今求められているACP(アドバンス・ケア・プランニング)14)も、必ずしも終末期の医療の選択だけに着目するだけでなく、「死ぬまでにやりたいこと=BUCKET LIST(バケットリスト)」をあげて、ケアマネジャーや主治医や訪問看護師たちとACPのための対話を重ねていってほしいのです。
☞BUCKET LIST(バケットリスト)
“bucket list”とは「死ぬまでにやりたいことのリスト」。“a list of things you want to do before you kick the bucket”ということになるのですが、ここでの“kick the bucket”とはどのような意味かわかりますか?“kick the bucket”は直訳すると「バケツを蹴る」ですが、実はこれで「死ぬ」という意味に(語源は諸説あるよう)。“bucket list”は、この“bucket”と“list”を組み合わせた造語です。さて、What’ on your bucket list?(あなたのバケットリストにはどのようなものがありますか?)
※「おしゃれもキャリアも。働く女性のWebメディア 「bucket list」の意味は? バケツのリスト… じゃない【連載 大人の英語塾】」より引用 https://oggi.jp/6925748
2023年12月13日アクセス
◎まとめ―よりよい「死」を考えることで「生」が輝く
失ったものではなく、残された「生」の時間に目を向けてもらうアクションが自殺予防の近道だと思います。高齢者にとって「死」は縁起でもないことではなく「もうすぐ起きること」です。「こんなふうに死にたいな~」と考えてもらうことで、それをかなえるために「今できること、今やりたいこと」が浮かんでくるように思います。
「死」までの残された時間に何をやりたいのかを考えることは、きっと「生きる意味」を見出すきっかけになるはずです。周囲の人は高齢者自身の「やりたいこと」を引き出し、実現に向けたサポートをする……それこそが何よりの孤独死・孤立死、そして自殺対策だと「小さな灯台」は考えます。
ACPの話題を、単に蘇生術や医療処置の有無だけに限定せず、BUCKET LIST(死ぬまでにやりたいこと)を話題にすることが当たり前の社会、それをサポートして実現する・させることを歓びとするような社会的風潮が育つことを願わずにいられません。
【参考文献】
1)令和6年中における自殺の状況 厚生労働省自殺対策推進室 警察庁生活安全局生活安全企画課 20250427 https://www.mhlw.go.jp/content/001464717.pdf
2)斉藤雅茂:日本の高齢者の社会的孤立と自殺死亡率:7年間の追跡調査, Social Science & Medicine 4月号,2024
3)令和2年版自殺対策白書 第2章第4節「後期高齢者層における自殺をめぐる状況」https://www.mhlw.go.jp/content/r2h-2-4.pdf
4)令和3年版自殺対策白書 https://www.mhlw.go.jp/content/r3h-1-1-07.pdf
5)令和6年版自殺対策白書 https://www.mhlw.go.jp/content/001321212.pdf
6)長田賢一,中野三穂,御園生篤志,高橋清文,高橋美保,長谷川洋,金井重人,貴家康男, 田中大輔,渡邊直樹,山田光彦,朝倉幹雄:高齢期のうつ病と自殺予防対策,精神保健研究第19号(通巻52号): 49-58,2006
7)特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンクhttps://lifelink.or.jp/
8)厚生労働大臣指定法人・一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター https://jscp.or.jp/
9)張賢徳,中原理佳: 特集 老年内科医に必要な精神神経疾患の知識 3.高齢者の自殺, 日老医誌 2012;49:547―554
10)健康長寿ネットhttps://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/seishinshikkan/zisatsu.html
11)名古屋市健康福祉局健康増進課精神保健係(いのちの支援)「高齢者の自殺予防ハンドブック」(令和5年3月発行)
12)佐藤惟:人生会議のソーシャルワーク―単身高齢社会で「希望」をつなぐ福祉実践-,風鳴社,2025
13)猪熊律子:塀の中のおばあさん―女性刑務所、刑罰とケアの狭間で―,角川新書(2023年3月発行)
14)会田薫子編:ACPの考え方と実践―エンドオブライフ・ケアの臨床倫理―,東京大学出版会(2024年3月発行)