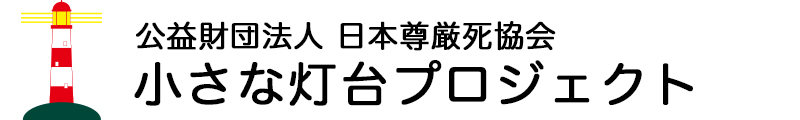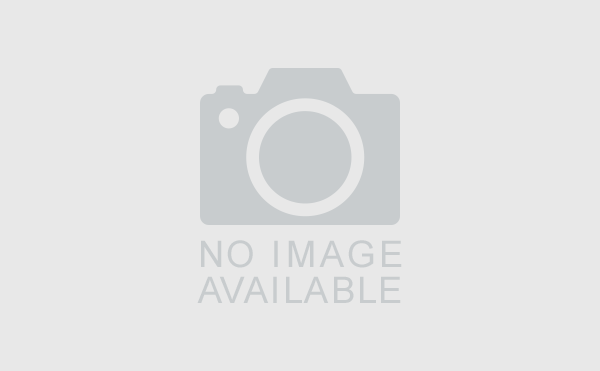医師から本人への余命告知に納得いかず
遺族アンケート
81歳夫/看取った人・妻/秋田県/2024年回答
大学病院の担当医師、看護師のみなさんは大変よくみてくださり、こちらの介護者の申し出を受け入れてくださいました。特に症状が悪化し、終末医療の際、ホスピスが満床で入院できなかった1か月間、特別に病院側で終末医療をしてくださり、大変ありがたく思っております。
ただ最初の入院(2021年11月11日)後、頭のレントゲンを撮影した時点(手術前)で、本人含め家族(妻、子ども2人)に余命半年か1年と告知されました。医師は「今は告知が義務となっております」と言われましたが、本人の気持ちを考えると、せめて本人には後日家族から話したかったと思っております。
それでも本人は、亡くなるまで自分の余命に関して一言も言わず逝ったことを立派だと思ってはいます。私としては受け入れ難く思っております。
協会からのコメント
がんの告知が一般的ではなかった1990年代、医療従事者もご家族も嘘をつき続ける中で、さまざまな苦労を経験しました。そんな環境の中で、山崎章郎医師による『病院で死ぬということ』という本がベストセラーになり、患者の尊厳を守る医療のあり方を問いかけました。その後告知が義務になるという変化を迎えて一番良かったことは、医療従事者もご家族も「本心でのコミュニケーション」ができるようになって、多くのご家族が「気持ちが楽になった」と感想を述べられるようになったことです。それでも、「病名や余命の告知」を受けることは、患者さんやご家族にとっては人生が変わってしまうほどの出来事です。
つらい事実を伝える際、患者・家族との感情の行き違いをできるだけ減らし、むしろその後のご家族の支えとなるようなコミュニケーション・スキルを磨き続ける努力は、今や医療従事者の義務になりました。そのための専門看護師や医師の人数も増えてきましたが、まだまだ一般的とはいえません。一方で、「いつかは誰にでも起こること」として、一般市民の中でもつらい出来事を受け止められる「心の筋トレ」を続ける努力が望まれています。
いつかは誰にでも起こる「大切な人との死別」という「つらい経験」を受け止められる「心の筋トレ」のサポート役を、「小さな灯台」が果たせるようにと願っています。
ご冥福をお祈りしております。