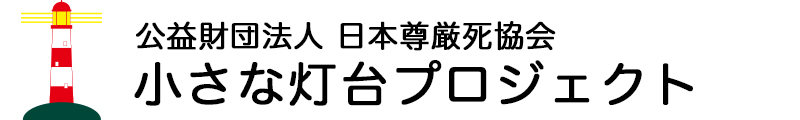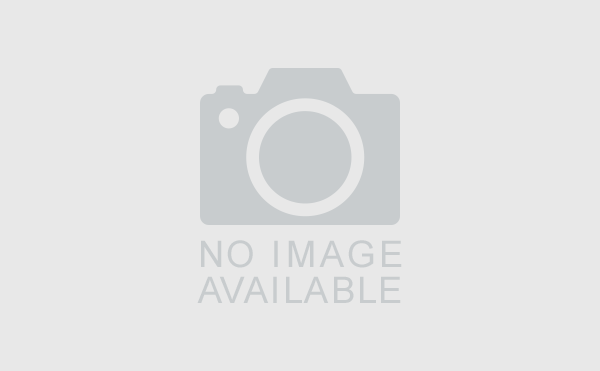わかりにくい……どこからが延命治療?
遺族アンケート
91歳父/看取った人・息子/大阪府/2024年回答
父からは延命治療を拒否する旨を明確に伝えられており、私もその意思に沿うつもりでおりました。しかし、どこからが延命治療なのかという認識が、私には欠けておりました。
父は誤嚥を繰り返して肺炎が悪化していったため、口からものを食べることができなくなり、最期の数か月は点滴だけで栄養を摂っていました。恥ずかしながら、このような状態も延命に当たるという考えがあることを、後になって知りました。
確かに、食事もできず一日中寝たきりという生活は、とてもつらかったのではないかと思います。父が意思表示をできる状態であれば、治療を止めてほしいと言ったかもしれません。もっとも、私から点滴を止めてくれと言うこともできず、どうしてよいのかわかりませんでした。
病院や医師を責めるつもりは全くありません。ただただ私の勉強不足が原因です。将来、自分が看取られる側になる際に、この経験を活かしたいと考えております。
最後になりますが、貴協会には長い間お世話になりました。ありがとうございました。
協会からのコメント
「口からものが食べられなくなった時、あなたはどうしたいですか?」という問いかけは、尊厳ある最期を望む人々にとって大事なキーワードであることがわかる「看取りのエピソード」です。
ご指摘のとおり、口からものが食べられなくなった時(=終末期)、「どこからが、何が、延命治療注1)になるのか?」……その時、直面している家族には「わからない」ものです。だからこそ、医療従事者に質問してよいのです。
その時、何を、いつ、どのように質問すれば良いのか? ということがわかるためにも、尊厳死協会が全国各地で繰り返し開催している講演会や、サロン活動に、より多くの人々が参加してくださるように、会員の皆様とともに、広報・啓発に務めていきましょう。ご協力いただけると幸いです。
一方、医療介護従事者にも意識して対話する姿勢が求められます。
「父が意思表示をできる状態であれば、治療を止めてほしいと言ったかもしれません。もっとも、私から点滴を止めてくれと言うこともできず、どうしてよいのかわかりませんでした」……「小さな灯台」は、この状況が家族にとってはどれほどつらく重い経験であるかを、医療介護従事者の方々に理解してもらいたいと思います。
リビング・ウイルやACP(アドバンス・ケア・プランニング)注2)は、尊厳死を希望する人々が、終末期における医療やケアについて、自ら意思決定を行うための大切なツールです。
それは、自分自身や家族のストレス、不安、抑うつを軽減し、「より良く生ききれた」と満足して最期を迎えるためにあります注3)。また、その意思を家族や医療介護従事者に理解・納得してもらうためにも重要な役割を果たすはずです。
2024年度診療報酬改定で、ACPを含め意思決定支援に関する院内指針の作成が、入院基本料算定の要件となり義務化されるようになりました。国もACPの推進を重要視していることがわかります。
一般市民にとって、ACPが何を意味するのかは、いまだ十分に認知されているとはいえないのが現状です。まずは、医療介護従事者側が終末期の医療ケアについて患者家族と対話することを、大切な診療行為として向き合う努力が望まれています。
ご自身の経験が次の“より良い経験”につながっていきますようにお祈りしております。
編集部注)
注1)延命措置=延命治療を含む、生命を延ばすためにとられる対応・手段。
以下、尊厳死協会HPより。
呼吸ができなくなれば酸素が体に入らず、やがて心臓が止まります。人工呼吸器を使えば、酸素が送られて心臓の動きは保たれ、数年生き続ける人もいます。このように生命に危険が迫った時、生命を維持するための措置が延命措置です。
延命措置として使われるものに、人工呼吸、人工透析、栄養・水分補給(経鼻管、胃ろう、中心静脈栄養など)、血液循環の維持、薬剤投与などがあります。
ただ注意したいのは治療措置と延命措置の関係です。本来、病状改善を目的とした治療措置であったものが、病状回復が期待できず、命の救助も不可能になると、同じ措置でも「治療」「救命」より「延命」の色合いが濃くなってきます。そして、もはや死が避けられず、単に死の時期を先送りする状況では、「延命措置」になってしまいます。
注2)
ACP(advance care planning)=人生会議
▶ACPの定義
「ACPは将来の医療・ケアについて、本人を人として尊重した意思決定の実現を支援するプロセスである」※ACPの実践のために、本人・家族等と医療・ケアチームは対話を通し、本人の価値観・意向・人生の目標などを共有し、理解した上で、意思決定のために協働することが求められる。
▶ACPの目標
本人の意向に沿った、本人らしい人生の最終段階における医療・ケアを実現し、本人が最期まで尊厳をもって人生をまっとうすることができるよう支援することを目標とする。
出典:日本老年医学会「ACP推進に関する提言」2019
注3)「ACPには、終末期ケアの質を向上させ、患者と家族の満足度を高め、家族のストレス、不安、抑うつを軽減する効果がある」とする海外の論文もあるほど重要で、日本における検証・研究も待たれています。関心のある方は下記をご参照ください。
Detering KM, Hancock AD, Reade MC, Silvester W.The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial.BMJ. 2010;340:c1345. doi:10.1136/bmj.c1345.