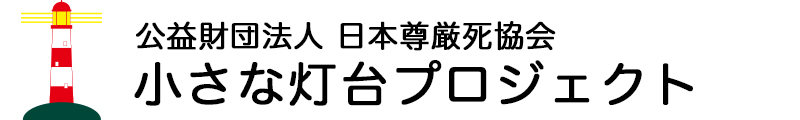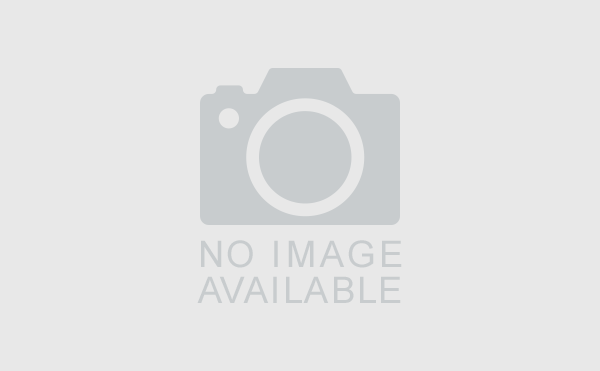人工透析を止めて刑務所に入ってもいいとまで考えた父の看取り
東京都中央区 民生委員
鈴木雅之
父の脳梗塞と次々に迫られる決断
その日も、いつもと同様に父を迎えに透析の病院へ向かいました。入口に近いベッドで事後の処置を待っているところでした。来たことを知らせようと合図を送ったのですが、
父の目の焦点が定まらず、ゆっくりと周囲を見回しています。看護師さんも気づいて処置が始まりました。やがて脳梗塞らしいこと、救急車を手配したことを告げられました。
搬送されたかかりつけの大学病院では「脳出血の既往歴もあり、できる処置が限られるために回復は困難である」と告げられました。86歳でした。
父の告知の後は、覚悟していたこととはいえ、延命措置の有無、退院にともなう受け入れ先、そして胃ろうの問題と、次々に決断を迫られます。積極的治療をしないということは、退院を意味します。透析があるために自宅には戻れませんし、介護施設の受け入れも不可、透析ができる病院を探すことになりますが、そのためには胃ろうがあったほうが探しやすいとの話もありました。
刑務所に入ってもいいとまで考えた父の看取り
幸い数日で、胃ろうなしでも受け入れてくれる病院が見つかり、無事転院いたしました。その数日間には弟との話し合いで、最終的には自宅に連れて帰り、透析を止める選択肢もあるとの話をしましたが、弟に「そんなことをしたら会社にいられなくなる」と反対されました。もっともなことなのですが、その時には私が刑務所に入れば済むことだとまで考えていました。父は8日ほどで転院先の病院で亡くなりました。
尊厳死協会へ入会
父は60代のころに、母ともども尊厳死協会に入会しました。民生委員を務めていましたので活動の中で尊厳死協会のことを知ったようです。私たち兄弟も、入会と同時にそのことを知らされました。普段からの会話の中で両親の考え方はわかっていましたので、ごく普通のこととして受け止めていました。父の死後、私たち兄弟も協会に入会いたしました。
「リビング・ウイル」……伝えたいのに伝わらない
その後、私も民生委員をお引き受けすることとなり、地域の老人会にも加わり現在運営に携わっています。老人会も高齢化が進んでいますので、リビング・ウイルのことはぜひ知っていてほしい知識であろうと考えました。会に馴染んできたころに、父の看取り体験の中での医師とのやりとりなどと共に、尊厳死協会のお話もいたしました。しかし話が下手なこともあり、今ひとつピンとこられなかった様子でした。老人会のメンバーは人生の大先輩も多いので、私の腰が引けてたのかもしれません。
医師から「回復の望みはありません。さあ、どうしますか?」と決断を迫られる場面は突然に、しかし誰にでも起こりうることなのです。悲しみで混乱しているその時に、「『父はこう言っていました』という本人の意志(リビング・ウイル)があれば、決断の大いなる助けになります。そして、その本人の意志の事実を担保してくれるのが尊厳死協会なのです」と説明するのですが……。
もっとも死生観は人それぞれです。私の妻も入会を拒否いたしました。嫌なことは見たくもないし、考えたくもないというのもわからないではないのですが。
自分の終末期の意志を定めておくことは、遺された家族の心の負担を大きく減らすことにもなります。とはいえ、遺言書の問題と同じで、元気なうちに家族でよく話し合って全員が納得していないと意志どおりにはならないこともあるようです。尊厳死の問題も、この「元気なうちに家族でよく話しあって……」が高いハードルであるように思います。
「尊厳死・ACP」をテーマにした民生委員の勉強会で手応え
先日、地区の民生委員の部会研修に「小さな灯台プロジェクト」リーダーの近藤和子先生を講師にお迎えして、尊厳死・ACPについての勉強会をさせていただきました。
*ACP=アドバンス・ケア・プランニング(人生の最終段階の治療とケアのプランを考えること)
その議題の選考時においても「尊厳死は法的にグレーゾーンなのではないか」また「尊厳死協会という特定の団体に肩入れするようなことも、民生委員の研修としては不適切なのでは……」という意見もあがりました。それには、日本では法的に認められていない安楽死との違い、あまり聞きなれない尊厳死協会の設立意義を説明して、スピリチュアルな団体などではない、あくまで「終末期の自分の意志(リビング・ウィル)を担保してくれる組織であること」等を丁寧に説明して納得していただきました。
加えて、近年ご親族を亡くされ、ACPの必要性を痛感された役員の賛同意見の後押しもあって、研修議題を成立させることができました。
研修会では、疑問点を納得いくまで講師とお話しできるように、質疑応答の時間を長く設定いたしましたが、質問が途切れることもなく、後日、出席者より「あまり考えてこなかったことを教えてもらい勉強になった」との声をいただきました。
尊厳死協会を知ってもらう活動を始動
それにしても民生委員の間でも尊厳死協会の知名度は想像以上に低いものでした。協会関係者のご苦労は察するに余りあるものです。
この度の研修を通じて、そのころのことが思い出されて、私もまた、尊厳死協会を知っていただけるよう、再び活動を始めたいと思うようになりました。
近隣の町会、老人会に声をかけて、近藤先生のお話を聞く会がもてれば、少しずつでも関心と理解が広がっていくように思います。
両親が早い時期に入会し、そのことを当たり前のこととして受け入れてきましたが、それでも、医師から「どうしますか?」と決断を迫られると、つい「点滴だけでも」と楽な選択・決断に逃げたくなってしまうことも経験いたしました。
知っていれば無駄に悩むことを減らせます。微力ですが地域での活動を通して関心をもってもらえる場をつくれればと、今、考えています。
尊厳死協会には感謝しかありません。