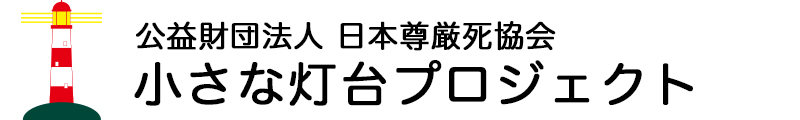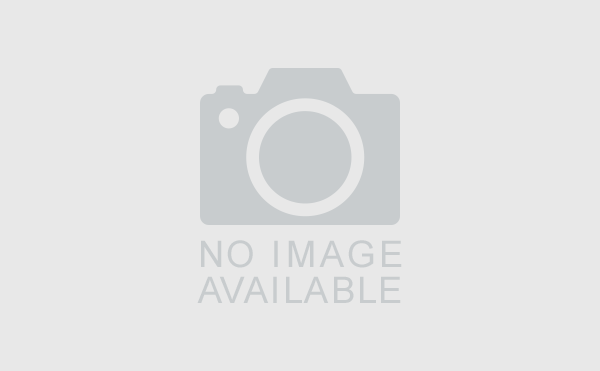超高齢者の心得
遺族アンケート
99歳姉/看取った人・妹/北海道/2024年回答
姉は特別養護老人ホームに入居していましたが、5月に脳出血になり、救急車で運ばれ、医師から「手術はできなく、状態も悪く、今日か明日」と言われました。なんとか8月までもち、別の病院に移され、そこで亡くなりました。救急搬送された病院の先生や転院先の病院の先生にも、リビング・ウイルカードを見せ、「わかりました」と言ってもらいました。亡くなる時は苦しみませんでした。
98歳おば/看取った人・甥/東京都/2024年回答
一番良かったことは、本人が元気なうちにリビング・ウイルについて話し合っており、終末期の医療措置について判断する際に、リビング・ウイルに沿って対処できたことでした。
骨折して手術・リハビリ後、一人暮らしが困難になり、やむを得ず施設に入所することになりましたが、その際にリビング・ウイルを提示することにより、終末期での介護について予め認識していただくことができました。実際に、終末期には本人の意向に沿った(尊重した)方法でケアしていただきました。
更に、施設に定期的に来所して診察してくださる訪問医の先生にも、リビング・ウイルをお伝えすることにより、終末期での医療措置について、事前に相談することができました。結果として、本人の意思に沿った措置で対処していただきました。
最後には、栄養補給だけの点滴も外して、穏やかに永眠することができました。主治医である訪問医のお話によると、点滴を外したことで、痰の吸引措置が不要になり、苦しみがほとんどなかったのではないかということでした。
最後に、私どもの反省点としては、個別の医療措置について、私どもの身内の誤解があり、医療介護スタッフとの思いのすれ違いが生じました。(結果的に良かったのですが)そういう意味では、個々の医療措置について、どういう痛みもしくは苦しみがあるのか、家族が理解できるよう情報が簡単にわかればいいなと感じました。
協会からのコメント
98・99歳という超高齢期に人生の最終段階を迎える人の心得として、「本人が元気なうちにリビング・ウイルについて話し合っておくこと」が当たり前の「生活習慣」になってほしいですね。それが超高齢社会を迎えた私たちの国の課題だと思います。
リビング・ウイルが明確に示されていたことで、一人暮らしから、施設、病院、訪問医師が、関わるそれぞれの場面で、本人の意思に基づいた役割を果たしてくださった様子がよく伝わる「看取りのエピソード」です。
看取り期の医療措置について、どういう痛み、苦しみがあるのか、その対処策について家族が理解できる情報の普及啓発活動も、私たち尊厳死協会の大事な役割です。「小さな灯台」も、会員の皆様のおひとりおひとりの経験をご紹介することで、ご家族の皆様が「看取り期の対処の仕方」を理解していただけるように工夫を重ねてまいります。【情報BOX】日本尊厳死協会員のための【看取りの観察と過ごし方ガイド】―安らかに健やかに最期を過ごしていただくために、私たちにできること―でも、ご紹介していますので、ぜひご参照ください。
心からのご冥福をお祈りしております。