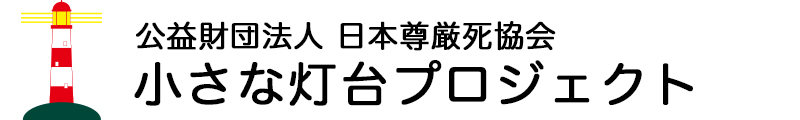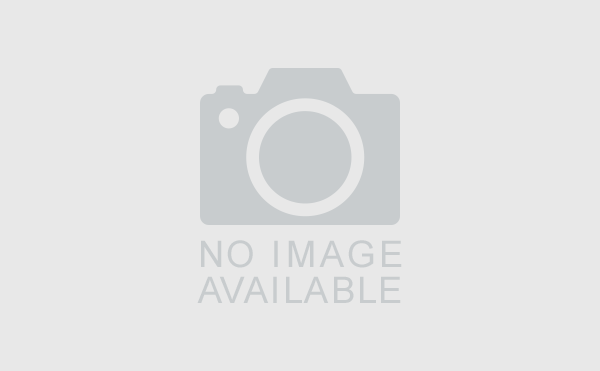緩和医療って何なの! と強い不信感
遺族アンケート
72歳夫/看取った人・妻/兵庫県/2024年回答
主人は今まで病気ひとつせずに元気だったので、100歳まで生きるつもりでリビング・ウイルに入りました。
延命治療は人に迷惑をかけると常々申しておりました。昨年1月末にステージ4と宣告され、抗がん剤治療も拒否し、あらゆる民間療法を試しました。しかし3か月ごとのCT検査で悪化していることが判明してからは、リビング・ウイルの記入欄には、最初と違って輸血、点滴、痛み止め等あらゆる治療を希望しておりました。私は、人間は究極の状態にならないと本心はわからないものだと痛感しました。
最期の3~4日は自分の意志もなく主治医に任せていました。
緩和病棟があるからとかかりつけ医にすすめられた病院に最期の5日間だけ入院しましたが、最期の2日は主治医が出張でほったらかしになり、看護師の連絡が遅く死に目に会えませんでした。また、かかりつけ医は、7月の診察の時に主人と私に「後1か月もたないわよ! もっと早いかも知れない」と凍りつくようなショックな言葉を平気で投げつけました。
その日から主人は一気に悪化して逝ってしまいました。それからはリビング・ウイルのことは忘れているようでした。心の中ではなんとしてでももっと生きたいと思っていたようです。
私は緩和医療って何なの! と不信感で一杯です。半年以上経っても心の傷は癒えません。
協会からのコメント
「私は緩和医療って何なの! と不信感で一杯です。半年以上経っても心の傷は癒えません」……全く、これこそが、ご遺族の気持ちそのものだと、この想いを多くの医療介護従事者の人々に知っていただきたいと思います。
生命体としての人間の本質は「治りたい」「病に勝ちたい」し、何としても「生きたい」のです。その想いとは真逆の流れに押し倒されていくのが死に逝く人の情況なのですから、腹立ちはいかばかりかとお察しします。
この哀しみにもプロセスがあることが、医科学の分野を基盤に、人文社会科学の諸分野でも幅広く研究されています。例えば、宗教文化の分野の高木慶子先生(上智大学グリーフケア研究所名誉所長)は死別の哀しみ(グリーフ)について実践的な発信を続けておられます。雑誌・婦人公論12月号(尊厳死協会とのタイアップ連載記事ページ)で、高木先生のインタビュー記事が掲載されていますので、ご覧いただければと思います。
今は、本当におつらいでしょうが、【情報BOX】グリーフケア-大切な人を亡くした哀しみを癒すためにもぜひ参考になさってみてください。
つらいお気持ちのさなかにもかかわらず、ご投稿いただき誠にありがとうございました。ご主人様のご冥福をお祈りいたします。奥様もくれぐれもご自愛ください。