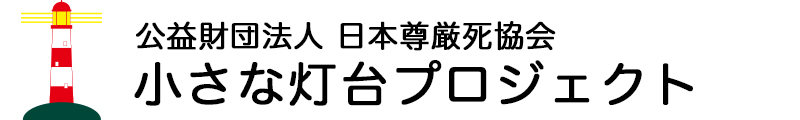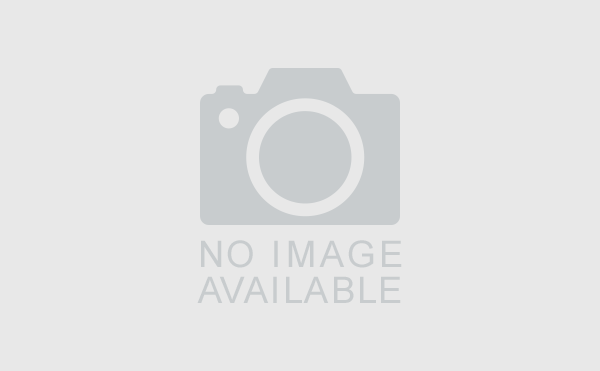希望を受け入れてくれる医師にかかると決めていました
【遺族アンケート】
76歳夫/看取った人・妻/静岡県/2023年回答
私たち夫婦は、延命治療は望まないという考え方を常にもっていました。医療を受ける時は常に書面のコピーを提出すると共に理解を求め、それを受け入れてくださる医師にかかることにしていました。
特に2015年から透析治療に入るにあたり、在宅訪問医に月に一度往診していただくことにしました。最初によくお話しして書類も提出し、何が起きても救急車は呼ばないことに同意していただいていたので安心できました。
ここ最近はとみに弱ってきましたが、私はできる限り自宅で世話することを希望し、週3日の透析も車で送迎していました。何とか自分の体力も保てるように、できれば自宅のベッドの上で私の見ている時に逝ってくれるようにとずっと祈っておりましたが、その通りとなり、最後に気を失ってからわずか30分で苦しむこともなく静かに息をひき取りました。すぐに医師に連絡して死亡診断をしていただきました。
私自身、8年半の主人の透析を支え続けることができ、介護を全うできたという感謝と安堵の思いです。そのことに、貴協会の会員であることは大きな支えとなってきました。「小さな灯台」のサイトもいつも読み、励ましを受けていました。ありがとうございました。
【協会からのコメント】
Moral distressという言葉があります。
自身の倫理観と違う考え方をもった人に対するケアの中で感じる苦悩・苦痛のことです。それは現場の医療者たちが必ず突きあたる壁です。
医療介護従事者が、患者さんや家族の生き方を尊重するためにMoral distress を感じる場合は、自身の気持ちと切り離してケアをしなくてはなりません。
どう個人個人と向き合うか、その人らしい生き方を全うするためにどんなケアができるか、それは医療・看護ケアの真髄であり、宗教というより医療倫理との向き合い方だと思います。
患者・家族に多様な希望や意見があるように、医療介護従事者にも多様な希望や意見があって当然だと受け容れましょう。大切なのは、お互いに違いを明確にして、違いを認識できること。そして、批評・非難して裁くのではなく、違いを認め、尊重できること。まさに「『ちがい』の中の『おなじ』と出会う(ユニセフ標語)」努力の積み重ねが、今こそ必要とされています。
また、私たちが自分に相応しい選択可能な道を探せる自由と選択肢が豊かに用意されていく必要もあります。
ご本人の意思を理解して尊重してくれる医療従事者との出会いは大きな力。医療従事者を選ぶことがどれほど大きな力になるか教えていただきました。
愛する人に安らかに看取られる最期を迎えられて本当に良かったですね。ご冥福をお祈りしております。