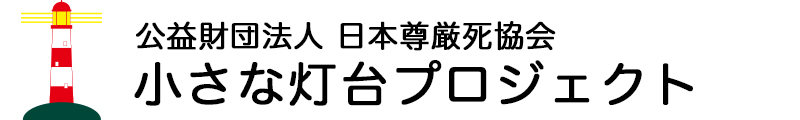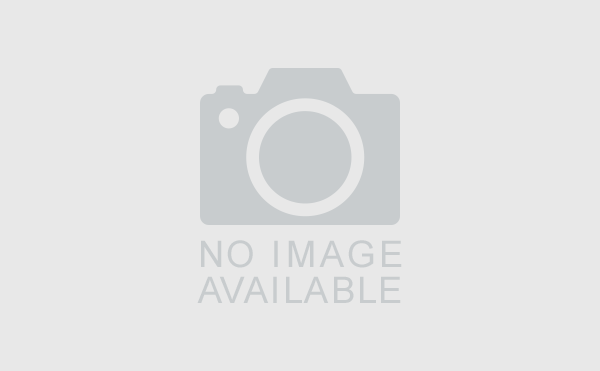「今後の医療方針を家族で決めてください」と言われて……
遺族アンケート
90歳母/看取った人・息子/滋賀県/2023年回答
施設にいた母が朝から急に体調を崩し、救急搬送されました。直接母と会えることなく、夜になって「今後の医療方針を家族で決めてください」と言われました。「母は尊厳死協会に入っています」と伝えると「では年齢から考えて過度な治療はしませんが、次の段階の酸素吸入はどうしますか?」と聞かれました。
結局お断りをして、母はその夜中に亡くなりましたが、長く苦しむことなく、判断は間違っていなかったと思っています。
ただコロナ禍の3年間でしたから、母と直接会ったり、手を握ったりすることができなかったことは、とても残念でなりません。
後から人に聞いたところ、次の段階の酸素吸入はとても苦しい(痛い)らしいです。やめておいて良かったです。実は母は7年前に脳出血で救急搬送されています。その時は「尊厳死協会に入っています」とは言いましたが、父(すでに亡くなっております)や家族が「できるだけの治療をしてほしい」と希望をしました。結果として車いすの生活になり、不自由をかけました。その時の判断が良かったのかどうかは今でも思い悩むところです。
治療方針を決めるということは本当に難しいことだと感じます。
協会からのコメント
治療方針は医師が決めてくれるものだと思っていたのに……。ある日、突然「どうしますか?」と聞かれ、次々に治療の選択を迫られる事態に苦悩しない人はいません。
だから「普段からACP(人生会議)について家族で語り合っておきましょう」と言われても、そんな気持ちになれない。公私ともに忙しくて、とてもそんな時間がつくれないという子ども世代が多いのもやむを得ない現実です。
また「尊厳死協会に入会している。話し合ってもきた」という理想的なご家族でも、いざとなると、それこそ反射的に「できるだけの治療をしてほしい」と言う言葉が出るものなのです。その結果についても、想像していたこととは違う、思いもよらない事態に出会ったりして「その時の判断は良かったのか」と思い悩み続けることも、誰もが経験することなのです。
決して、あなただけではありません。あなたはひとりではありません。同じような経験をした方々が、この「小さな灯台」に投稿してくださっています。
たとえ、どんな結果であったとしても「その時、その状況で、選択したこと・決断したことは最善だったのだ」と……。そう思って良いのだと、このつらい決断を経験した者同士、認め合いましょう。支え合いましょう。
そして「命の選択・決断」をした方々を優しく受け容れ、繰り返し慰め、前に進むことを後押ししてくれる社会的風潮を育んでいきましょう。「小さな灯台」はいつでも、あなたの味方です。くれぐれもご自愛ください。