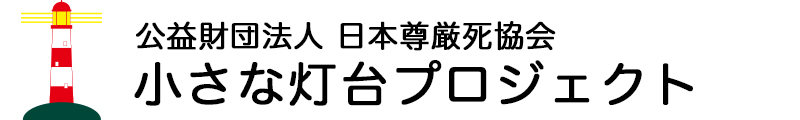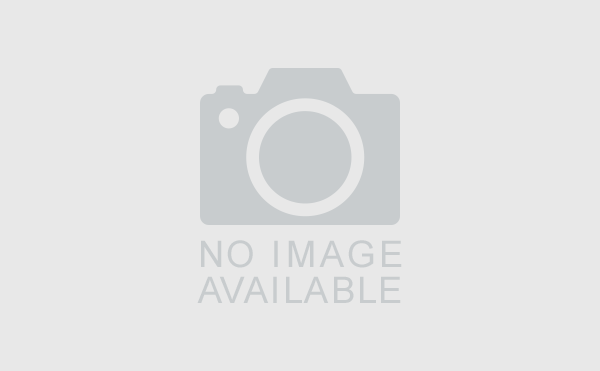リビング・ウイルを代弁するために
遺族アンケート
●本人に代わって主治医に伝え続ける
97歳母/看取った人・娘/大阪府/2024年回答
母は1992年に父とともに入会しました。2008年12月14日、父は亡くなる前に会員証を医師に見せ、何度も念押ししていました。そのことを思い、最後は自分で意思表示できなくなっていた母ですが、元気だった頃の本人の意思を、自分が代わりに会員証を持って主治医に伝え続けることができました。2023年12月14日、父の命日に母は逝きました。父が迎えに来たのでしょう。後日、戸籍を取り、午前と午後の違いがありましたが、同時刻であったことに弟と二人で言葉がありませんでした。
●どこまでの医療行為を望む?
91歳父/看取った人・娘/埼玉県/2024年回答
医師から「会員といっても人によって基準がいろいろあります」と言われました。入院時には、どこまでの医療行為を望むのか、細かく確認される時代です。知識が必要だと感じました。最終的には医師との相性も大切だと思います。うちは助かりました。本人は入会後、友人にも勧めていて喜ばれていたそうです。
●救急車を呼ばないように
97歳父/看取った人・娘/京都府/2024年回答
父、母(平成28年死亡)の担当医共に、リビング・ウイルのことを伝えましたら、救急車を呼ばないようにとアドバイスをいただき、無駄な延命治療を避けることができました。長い間お世話になり、ありがとうございました。
協会からのコメント
個人がリビング・ウイルの生き方を果たすためには、ひと言で言い尽くせない、さまざまな難局があります。ここにあげさせていただいた3人の方々、それぞれが体験された局面が、その多様さを物語っています。
▶1番目のエピソード
リビング・ウイルの会員証を持っているだけではだめで、ご本人が日ごろから、自らの意思であることを医師に話しておかなければならないこと。その行動を見ていたからこそ、娘さんは代諾者としての役割を果たす勇気と覚悟をもてたのだろうと察することができます。
▶2番目のエピソード
まさに「入院時には、どこまでの医療行為を望むのか細かく確認される時代です。知識が必要だと感じました」とのご指摘のとおりです。
ある日突然! 病気や介護で入院の必要を迫られ、初めて「どこまでの治療を希望しますか? 救命措置をどこまでしますか?」などと質問される。書面を見せられ、サインを求められる。一体何を聞かれているのか単語の意味すらわからないのに、医療者は忙しそうで、誰にどう聞けばよいのかもわからないという困惑の局面に立たされる人々がまだまだ多いのです。
本来、入院時にACP(アドバンス・ケア・プランニング)の書面を交わすことが、社会全体の常識として根付いていれば、こうした局面も簡単に乗り越えられるはずなのですが……。
このようなご家族の困惑や怒りはクレームにつながりやすく、病院関係者も「必要な知識の啓発活動(患者教育)」に取り組んでいます。しかし、それは病院に来た人にしか届かず、病院に来る前の人々への、知識の準備教育まで関与できない困難さに直面しています。
▶3番目のエピソード
ACPを理解し、取り組み始めた患者さんやご家族にとって「救急車を呼ばない」という知識を、実際の行動に移す覚悟が必要になります。
3つのどれかではなく、全部必要なこと。誰もがその全ての難局に直面するのか? というとそうではありません。だからこそ、さまざまな局面を経験された人々の「看取りのエピソード」を、繰り返し「見たり、聞いたり」しておきましょう。いつか、きっと「わが身に起こった時」の参考になるはずですから。
ご両親の「個人の意思 リビング・ウイル」を代弁し、全うされたご遺族の方々に、改めて心からの敬意を表しつつ、ご冥福をお祈りいたします。