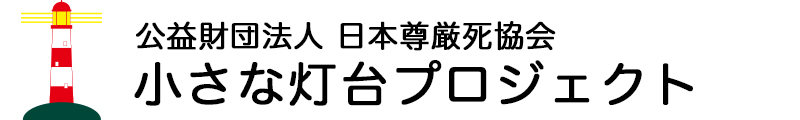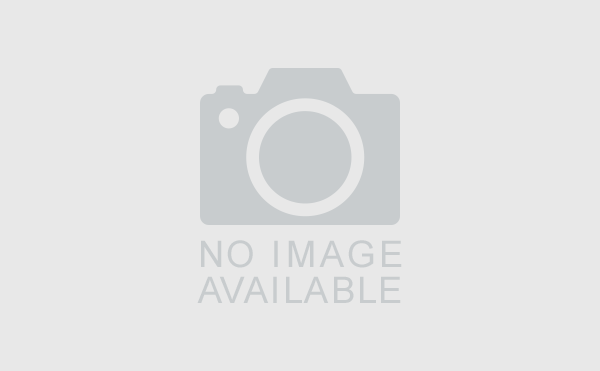【情報BOX】「代諾者(医療代諾者)」にリビング・ウイルを託す
本人が意思表示できないような場合に、代わりに医療的な希望を述べてもらう人を「代諾者(だいだくしゃ)」といいます。代諾者は、家族・親族でなくても、友人や信頼できる第三者になってもらうこともできます。ただし「代諾者」には法的担保がないため「対応が医療機関によって異なる」「トラブルになる可能性がある」など留意しておくべき点がありますので、それも含めて解説します。
◎医療における決定権は本人にのみある
「幸福追求権」といわれる憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と書かれています。これは、自らの意思で、生命に関することを決定する権利が保障されているということです。
この決定権は、本人のみ行使できるもので「代諾者」には法的根拠はありません。家族が「代諾者」であっても、家族の意思ではなく、あくまでも「本人の意思」に基づいた希望を伝えることが大前提です。
◎誰にもリビング・ウイルを伝えていなかったら……
「代諾者」を決めず、誰にもリビング・ウイルを伝えていなかったらどうなるでしょう。医療は人の命を救うことが使命です。救急搬送されて意識がないような状況では、残念ながら「リビング・ウイル」は実現されない可能性が高いといえます。
医療者も「本人の意向を尊重したい」と思っています。しかし、ご本人の意思を明確に確認する手段がなければ、ご家族に聞き、ご本人の意思を推測した上で判断しなければなりません。もしも「代諾者」となる家族がリビング・ウイルを知らなかったり、納得していない場合には「ご家族の意思」が優先されてしまうことになりかねません。
◎本人・代諾者・医療者の対話がリビング・ウイルを果たす力に
上述のように、生命の重要な判断が「救命優先」「家族優先」にならないためにも、本人が「代諾者」「医療者」を選び、常日頃から意思を伝え、納得してもらっておくことが大事です。「尊厳死協会への入会」というような書面に表す行動が伴っていれば、ゆるぎない意思を伝えることができるのではないでしょうか。ピンピンしていて医者いらずだった人が突然倒れたという場合でも、「代諾者」が本人の意思を十分理解していれば「医療者」と丁寧に対話することで、本人の意思は尊重される可能性が高くなると考えられます。
◎「代諾者」は誰がなる?
「ご本人の治療・ケア方針の希望」を代弁する「代諾者」の役割は、「キーパーソン=患者側のケア責任者」が担います(参照:【情報BOX】看取りのプロセスで家族が果たす役割 No.1 キーパーソンとは?)。キーパーソンは「本人が信頼を寄せる人」になってもらうのが一番です。ただ「代諾者」は、責任も負担も大きいことから、ご家族になってもらうことが多いでしょう。
しかし、一人暮らしの高齢者が増え、身寄りがない、家族と疎遠、家族も高齢、などさまざまな事情で、第三者に「代諾者」を頼まざるを得ないケースは確実に増えていくと思われます。「自分の希望を誰に託すのか」は真剣に考えなくてはならないテーマです。
◎家族以外、誰に「代諾者」をお願いする?
家族以外に「代諾者」をお願いするとしたら、どのような人が考えられるでしょう。
- 友人 ※大親友レベルの人でなければ難しい
- 信頼するケアマネジャーやケアスタッフ ※ケア職の本来の業務ではありませんので、業務量的に難しいのが現状
- 後見人 ※成年後見人は主に資産管理が役割、医療的判断はできないことになっています(医療同意権はない)。つまり「成年後見人を指定=代諾者の指定」ではありません。
- 業者(身元保証サービス業者など)※業者のサービス内容はバラバラで、すべての業者が医療方針の希望を伝えるサービスを提供しているわけではありません。
▶身元保証サービス業者の留意点
最近では「人に頼むより気が楽」ということで、「身元保証サービス業者」を希望する人が増え、業者の数もここ数年で急速に増えています。ただし、法規制が追いついていないこともあり「契約したサービスが提供されない」などの問題も起き、政府も利用者保護に動き始めています。2024年6月に、内閣官房・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省・ 法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省が連名で「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を出しています。省庁をまたがっての大関心事であることがわかります。業者を選ぶ際には下記のガイドラインを参照し、信頼できる人にも相談し、優良な業者を選びましょう。
・2024年6月 内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム) 内閣府 孤独・孤立対策推進室 金融庁 消費者庁 総務省 法務省 厚生労働省 経済産業省 国土交通省:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン
https://www.soumu.go.jp/main_content/000951820.pdf
◎第三者に「代諾者」をお願いする時の留意点
さらに家族以外に「代託者」をお願いする時には次のようなことを考慮する必要があります。
- 責任が重い・負担が大きい
・精神的負担……生死の判断に関わることですので、精神的に「荷が重い」のは確かです。リビング・ウイルの場合は「死の決断」ですのでなおさらです。
・時間的、金銭的負担……病院を訪問、医療者と対話する時間、交通費等金銭的負担もあります。 - 家族(親族)がいる場合にはトラブルになるケースもある
・ご本人とご家族の意見が違っていた場合、死後にトラブルになるケースも考えられます。また、ご本人が亡くなることにより年金がもらえなくなって家族が困る……というような場合もあります。 - 対応が医療機関によって異なる
・「代諾者」の役割に関しては法律の根拠がありません。とても曖昧な領域ですので対応が医療機関によって異なります。「家族がいるのに第三者が代諾者になっている」場合には、死後に家族からのクレームにつながることも考えられますので、医療側としても慎重にならざるを得ないでしょう。
◎トラブルから「代諾者」を守るために
- 本人の明確な意思表示(=リビング・ウイル)を書面にする
「代諾者」であるご家族や第三者が、他のご家族を説得するためにも、心の負担を軽くして迷いを減らすためにも、意思表示を記載した書面をつくりましょう。これは、反対するご家族によるクレームから「代諾者」を守ることにもなります。 - 契約書面
「代諾者」の役割を全うするには、時間的負担・金銭的負担もあり、労力がかかります。厚意で、無償でというわけにはいきません。特に第三者にお願いする場合には「必要経費の支払い・謝礼(報酬)」に関して明文化しておくことが大事です。「代諾者」が家族の場合「水臭い」「家族だから当然だ」とお金のことを曖昧にしがちですが、契約書面は家族の間での不公平感(モヤモヤ)を調整することにもなると思います。
※医療方針を伝えるサービスを提供している業者を「代諾者」にする場合には「契約書面」はより重要です。
日本では、人生の最終段階の医療について、明確に意思表示している人、ましてやそれを明文化している人はごくわずかです。「最期は家族や医療者に任せる」という人も多いでしょう。しかし、それは家族や医療者を、迷いや後悔でつらい気持ちにさせてしまうことになりかねません。ご本人もご家族も医療者も「満足な最期だったね」と思えるよう、今、行動を起こしましょう。
【参考資料】
1)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査(総務書,2023年8月)2025.2.4アクセス
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230807000167327.html#kekkahoukoku
2)臨床医の成年後見制度および医療同意権全般に対する認識を明らかに 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 2025.2.4アクセス
https://www.tmghig.jp/research/release/2024/0530.html
3)手術同意書のサインは家族以外でもOK?身元保証人の必要性や身寄りがいない場合の対応策も解説 セゾンのくらし大研究 2025.2.4アクセス
https://life.saisoncard.co.jp/family/preinheritance/post/c2912/