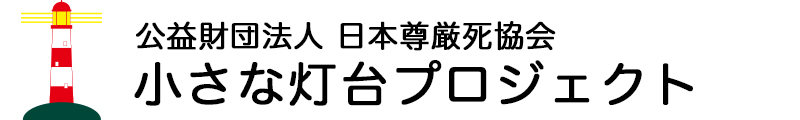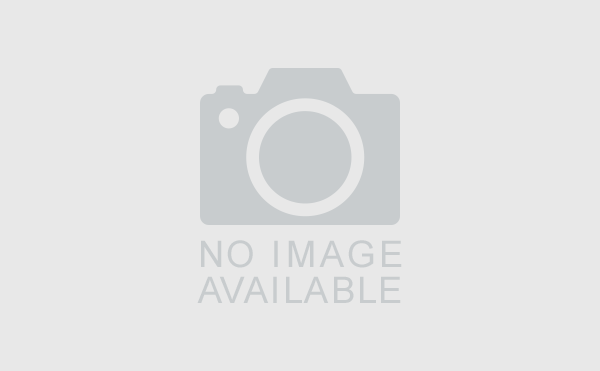「看取り」とは 無理な延命治療を行うことなく「人間の尊厳」を保ったまま亡くなるための支援
患者本人・家族・医療者の三位一体のハーモニーが織りなす見事な「看取りのエピソード」を6例ご紹介します。
【情報BOX】「代諾者(医療代諾者)」にリビング・ウイルを託す
看取りエピソード
医師から胃ろう・点滴を聞かれたタイミングでリビング・ウイルを提示
【遺族アンケート】(97歳父/看取った人・娘/東京都/2023年回答)
今年の2月半ばより身体のむくみがひどくなり、在宅での利尿剤では改善しなかったので、3月2日に病院の循環器内科に入院し、心不全と誤えん性肺炎の治療を受けました。
食事も1割ぐらいしかとれなくなってきたので、担当医から「胃ろうや点滴栄養はどうされますか」と聞かれたタイミングで、リビング・ウイルを提示しました。医師は大変よく理解してくれ、退院して「在宅看取り」をする許可を出してくれました。家で平穏に旅立つことができて家族は大満足でした。
いつ病気になり、死ぬことになるかわからない
【遺族アンケート】(76歳母/看取った人・娘/京都府/2023年回答)
ホスピスに入院したこともあり、すべて受け入れてくださったと思います。病状が悪くなると本人はとてもつらい日々を送らなければいけませんでした。なので本人の意志通りにできたことで、つらい延命にならず良かったと思います。母の死後、私も入会しました。母の時のようにいつ病気になり、人は死ぬことになるかわからないですから…
認知症になってもリビング・ウイルを周知していたおかげで……
【遺族アンケート】(90歳母/看取った人・娘/神奈川県/2023年回答)
本人は認知症になってしまいましたが、尊厳死協会会員であることを周知していたので、周りの協力のもと、穏やかに最期を迎えることができました。かかりつけ医、在宅訪問医、施設のお医者様、ともによく理解してくださいました。
本人が「手術はしません」と
【遺族アンケート】(94歳母/看取った人・娘/大阪府/2023年回答)
5/2に母がしんどいと言ったので急きょ大きな病院へ。2週間の入院で大腸がんのステージ4と言われました。先生に尊厳死協会に入会していると伝え、「手術はしません」と本人が。「では自宅でみられるなら在宅訪問医を決めてください」と。
訪問医の先生にも入会していることを伝えると「自宅で最後まで過ごせるよう見守ります」と言っていただきました。看護師さんも頻繁に訪問してくださって、最後まで好きな物食べて、好きに過ごして、最後の10日ほどは効果的に痛み止めをいろいろしていただいて、眠っているような最後でした。
2か月はあっという間でしたが、リビング・ウイルを皆様がスムーズに受け入れてくださり理想的な最後の迎え方だったなぁと振り返って、皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。母はずいぶん長く尊厳死協会に入会していましたが、おかげさまで心丈夫だったのではと思っています。ありがとうございました。
死は良き「生」の終着駅、そのための尊厳死
【遺族アンケート】(89歳母/看取った人・娘/奈良県/2023年回答)
終末期と施設の方に告げられ、施設長、施設看護師、相談員、そして担当医師の方々と話し合いをいたしました。「酸素吸入と点滴のみ、それ以上の治療は尊厳死の立場からしないと、家族としても望まない」と申した時、施設の方々もホッとしたように見受けられました。
やはり、本人が生前から最終の治療の意志を示し、形にしておくことは大事かと思いました。これからももっと尊厳死について世間に広める活動をお願いします。尊厳死と安楽死の違い等も広めていただきたいと思います。最近、尊厳死と安楽死の違いがあいまいな方が、安易に安楽死を主張していることがあるように思います。死はあくまでも良き生の終着駅であってほしいし、そのための尊厳死だと思います。
母の意志を思い、点滴をはずしてもらいました
【遺族アンケート】(92歳母/看取った人・娘/山形県/2023年回答)
母はずっと同居していましたが、2か月入院して家での看護は無理となり、施設で1年と9か月お世話になりました。
コロナで面会ができなくて切ない思いでした。家にいる時から先生には月1回訪問していただき、尊厳死協会に入っていることは話しており、施設に入ってからも診ていただいておりました。
口から食事ができなくなり、点滴を2日ほどしていただきましたが、母の意志を思い、点滴をはずして自然に眠るように息を引き取りました。尊厳死協会に入っていることで私も納得して見送ることができました。良い先生と施設の方々のおかげで本当に良かったと思います。自分のことを話しておくことは大事なことですネ。ありがとうございました。
協会からのコメント
入院して治療しているプロセスの中で、在宅看取りへ移行するタイミングを図ることは、実は非常に難しい支援なのです。
早すぎても、遅すぎても「尊厳ある最期」を支援することはとても難しいことなのです。それこそ、ひとつとして同じ例がない。人の数だけ様々な人生の終結があり、その方が生きてこられたように旅立たれるのだなあ・・・としかいいようがありません。その姿に丁寧に寄り添い続ける支援のプロセスが看取りなのです。
リビング・ウイルの意思表示が明確だったお父様、意思表明ができる準備の整ったご家族(代諾者)、そしてリビング・ウイル受容医師および医療ケア職との出会い、という三位一体のハーモニーが「大満足の在宅看取り」を可能にした「看取りのエピソード」の数々です。
「看取り」とは、無理な延命治療を行うことなく「人間の尊厳」を保ったまま亡くなるための支援をすること。と「小さな灯台」は提唱しています。
この認識が広く市民の間に広まり、医療者も安心して「幸福な看取り支援」ができる社会になりますように。素晴らしい「看取りのエピソード」の投稿を本当にありがとうございました。これからもそれぞれの看取りの経験をご投稿ください。
ご冥福を心よりお祈りしております。