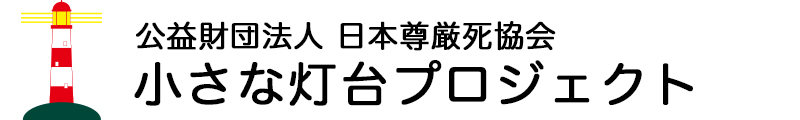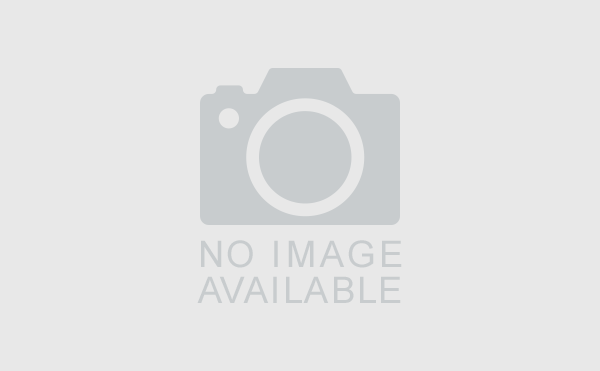半年の在宅介護で少しは親孝行できたかな
遺族アンケート
94歳義母/看取った人・長男の嫁/東京都/2024年回答
約半年ほどの在宅介護ののち、母は自宅で永い眠りにつきました。介護施設で誤嚥性肺炎となり救急搬送された病院で、入院後にどのような対応をするかソーシャルワーカーさんと打ち合わせしました。母はすでに93歳となっており、リビング・ウイルの意志表示もある旨を伝え、入院後の方針も納得する形で決まりました。
幸いにも1か月後に退院できるまで回復し、長男である夫と私の2人で、在宅介護をスタートさせました。
私どもは2世帯住宅で20年以上を親世帯と住んできたので、母にとっても「自宅」に帰ることができてとても喜んでいました(父はその2年前に他界)。
ただ、認知症も患っており、本当に理解できていたのかはわかりません。
在宅介護をはじめるにあたり、訪問医療を担当してくださる医師、看護師さんと打ち合わせした際にも、母がリビング・ウイルとして意志を記していた旨を伝えることにより、皆が看護・介護についてコンセンサスを得た上で、それぞれが母に向き合うことができました。今となっては、母がまだ元気なうちに、しっかりと意志表示をしてくれていたことに感謝するばかりです。
退院して家に戻ってきてからの1か月は、まだ体調も精神も安定せず、大変なことばかりでしたが、日々を重ねていく中で少しずつ少しずつ穏やかな時間が増して、笑顔も見られるようになりました。残念ながら母は旅立ってしまいましたが、半年の在宅介護で、私ども夫婦も最後に少しは親孝行できたかなと感じております。
先日一周忌を終えましたが、まだまだ母の(父も!)存在をそこかしこに感じながら日々過ごしている次第です。
これまでありがとうございました。送られてくる会報は私も拝読しておりました。
末筆ながら、貴会のますますのご発展をお祈りいたします。乱筆お許しください。
協会からのコメント
介護施設に入所していても、最期の局面で病院へ救急搬送され、病院から在宅医療へとつながっていった「看取りのエピソード」です。
こういう場合こそ、病院でも在宅医療の現場でも、ご本人のリビング・ウイルの意思表示がされていたことが、ケア体制を決めていく大きな助けになります。今後、ますますその必要性は高まることでしょう。
在宅介護には医師や看護師、さまざまな介護職がかかわるために、ご本人のリビング・ウイルが明確であれば、関係する職員のチームワークが取りやすくなるのです。
実際に体験した人でないと実感しにくいことではありますが、だからこそ、「実際はどうだったのか」「リビング・ウイルがどのように役立ったのか」を伝えることに意味があると感じています。もちろん、誰にでも当てはまるわけではないかもしれません。それでも、看取りや人生の最終段階は、誰もがいつかは遭遇せざるをえないことです。だからこそ、それぞれ異なる個人的な体験が、大切な学びや気づきを与えてくれるのだと思います。