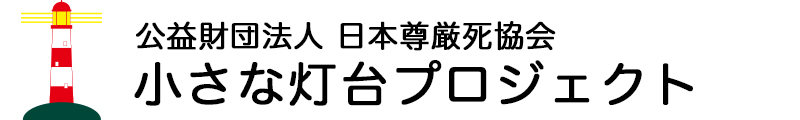終末期であるという自覚が持ちにくく、治療に揺れ動いていました。
遺族アンケート
LWについては、しっかり話をし、納得して本人が決めた事だったのですが、肺がん治療に関して、訪問診療になる前に、病院で治療を受けていましたが、担当医師から余命などの宣告もうけていないため、本人自身が「自分が終末期であるという」自覚が持ちにくかったようです。なので、病院から自宅に戻り、訪問診療に変わったのちも、もしかしたらまだ治療の可能性があるのではないかという思いと、これ以上は何も延命治療せずにいくという思いの間をゆれ動いていたようです。最後はこうしたいと決めていても、その最後が、いつなのか、正に今なのか、を自覚するのは本当にむずかしい事だと痛感しました。それは家族としても同じ事がいえると思います。全く未知の看取りまでの道筋でしたが、家族への丁寧な説明と症状に合わせた細かい訪問診療により、お別れに向けての覚悟とその時が来た自覚をもって、むかえる事ができました。延命治療をしないというのがどういう事なのか、とても良くわかり、すごく勉強になりました。おかげさまで、本人はほとんど苦しむ事なく静かに旅立つ事ができました。ただただ感謝しております。ありがとうございました。
協会からのコメント
看取りは「未知との遭遇」だと言われる情況が見事に表現されています。なぜなら、ご自分の状態が看取り期なのかどうかを知ることはとても難しいことだからです。医師にとっては“がんを根治する治療がなく、がんの増殖を抑えることができない状態が続くことが終末期だ”という理解の仕方だとしても、一方、昨日と変わらず生活できているのに、もう終末期なのか?と腑に落ちないという感覚こそが、患者家族の“あたりまえ”でしょう。だからこそ、「症状にあわせた丁寧な説明」がないと、「苦痛や生活上の困難がない状態である時間」を「やりたいことや伝えたいことを実行できる貴重な時間」にすることができないのです。
病院から在宅医療に変わるそのプロセスで、訪問の医師や看護師たちの“家族への丁寧な説明と症状に合わせた診療”という行為が、どれほど大事で効果的な“治療行為”であるかということをもっと多くの関係者に知ってほしいものです。
ひとりひとり違う「未知との遭遇」だからこそ、丁寧に、“看取りのエピソード”として紹介し続け、医療者にもご家族にも参考にしていただけるところに“小さな灯台”の役割があると思います。「お別れに向けての覚悟とその時が来た自覚をもつことができました」という言葉が何より素晴らしい“看取りのエピソード”です。