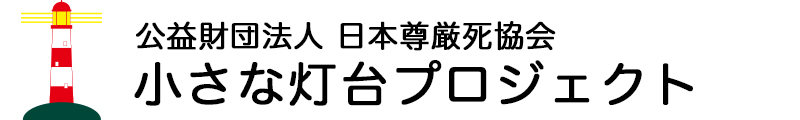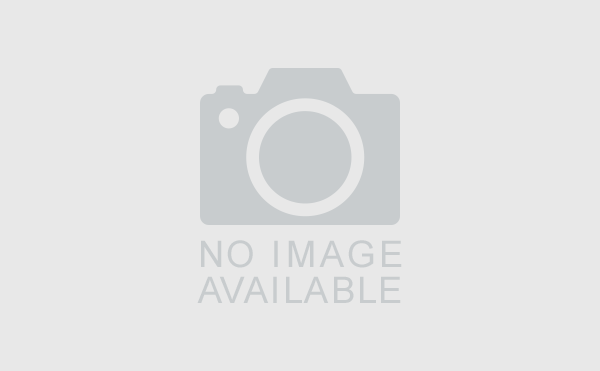尊厳死協会の医療相談に支えられて
遺族アンケート
98歳夫/看取った人・妻/埼玉県/2024年回答
かねてから夫と私は尊厳死の考えをもっており、会話の中でもたびたびお互いにその考えを確かめ合っておりました。最後は夫の気持ちに反することなく見送ることができ、何よりと思っております。
しかしそれはある意味たまたまのことであって、いろいろと考えさせられることもありました。
1月5日早朝、呼吸困難になり救急車で病院へ運ばれました。救急隊員の質問に「私の意思表示ノート」を見せて、延命措置は望まないことを伝えました。コロナによる39°の高熱で意識はほとんどなく、呼びかけに応えることもなく、酸素マスクを付けて苦しそうな息をしていました。翌日熱が下がり、意識が戻り「僕、死にそこなったよ」と笑うほどになりました。平熱になるまで隔離病棟で点滴を受け、面会も限られていました。
平熱になって3~4日目、主治医から次男に電話があり、「中心静脈栄養」の契約書にサインが欲しいとのことで、次男がOKしたということでした。「中心静脈栄養」について私たちは全く知りませんでしたが、夫の希望ではないと考えました。しかし次男は、父親の生命力を信じて「何とか回復してほしい」という思いから一度は承諾しました。ところが、それが父親の希望ではないと知り、すぐに承諾を取り消しました。そして私たちは、2日後に予定されていた主治医との話し合いを待つことにしました(尊厳死について直接主治医に伝えたのは主治医との話し合いの時が初めてでした)。
その間に、尊厳死協会の医療相談に電話をし、①尊厳死について病院側に再確認してもらう ②ホームの受け入れを確認する ③点滴は少しずつ減らす、などアドバイスをいただきました。心ゆくまで相談ができ、大変心強く思いました。
主治医との話し合いまでに、私たちは結論として「中心静脈栄養」は拒否することにしました。ところが、話し合いの朝と昼に、とろみ食を通常の1/3摂れるようになったので、主治医から「今回は『中心静脈栄養』は取りやめることにする」との話があり、私たちはとても驚くと同時に、ほっとしました。
ホームの担当医にも看護師にも、ホームで受け入れてもらい自然死を待つ考えを承諾してもらっていました。その考えをもったのは、何といっても、かねてから夫との話し合いの中で延命治療はしないとの約束があったからで、家族(息子二人)の思いは“エゴ”だと言って拒否したのです。
しかし、後になって考えてみますと……。夫が日々衰えていく姿を見ることに耐えられたか、夫との約束とはいえそれで納得できたか、という気持ちが大きくなってきました。幸い、最後は本人も望んだように延命措置に一切頼らず、静かに息を引き取りましたので、私たち家族としてもこれ以上望むことはないと感謝の気持ちでいっぱいです。
協会からのコメント
高齢だからといって、どんな病状にも救命に至る治療手段を何もしないというのが「尊厳死」ではないのです。その方の「生命力」を必要十分に引き出し、加減しながら慎重に見極めておられる主治医の姿勢がよく伝わってくる「看取りのエピソード」です。
「命は不思議」です。単なる年齢や検査値という数字では測れず、食べられないと思っていた人が急に食べるようになることもあります。そんな事態は誰にも予測できません。しかし、予測できなかったことでも、目の前の変化にきめ細かく対応していこうとする医療者の視点と努力があることも知っていただけますように。
ご家族の意見の違い、迷いに調整を図る方法として、「time-limited trial(お試し期間)」という考え方があります。以下にその内容をご紹介しますので、参考になさってみてください。
◎参考資料