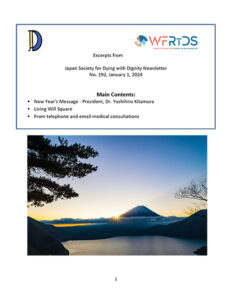厚生労働省の「認知症患者推計」に対する協会の見解
──1200万人「大認知症時代」に備えるために
2040年には65歳以上の高齢者のうち3人に1人が認知症か軽度認知障害になる──厚生労働省が5月8日に公表したところによると、認知症が584万人、軽度認知障害が612万人、軽度を含めれば計1200万人が「認知症」と見込まれています。国は今年1月に「認知症基本法」を施行し、認知症の人が尊厳を保ち最期まで希望を持って暮らせる「共生社会」の実現を掲げていますが、保険財政のひっ迫や介護離職の深刻化、さらに支える家族の側の疲弊など前途は多難です。
こうした厳しい状況に備えるには、一人ひとりそれぞれが認知症になる前に、どのような最期を生きたいのかという意思を確認し、それを家族や医療ケア従事者と共有しておくことが大事です。それにはリビング・ウイル(人生の最終段階における事前指示書) を準備しておくことが必要ではないでしょうか。協会が発行・普及に努めているリビング・ウイルは
●過剰な延命措置を希望しない ●緩和ケアは最期まで充分に行ってほしい ●家族や医療ケア関係者は自分の意思を尊重してほしい、という 3 か条から成り立っています。人生の最期についての「あり方」の希望がはっきりしていれば、本人はもちろん周囲の人たちも安心して生活することができます。 本人が病気になってからは、 医療従事者が中心になり「人生会議」(ACP:Advance Care Planning)を開いて意思や希望を確認する機会がありますが、何より大切なのは本人が周囲の雰囲気やアドバイスに影響されずに、自分で決定する意思です。
人の気持ちは常に揺れ動きます。 いったん決めたことでも撤回してかまわないし、 再び同じ考えに戻ってもかまいません。大事なのは、それをきちんと書面に残し、周囲と分かち合うことです。 自己決定し、それを分かち合うこと──それによって、認知症になっても本人の意思が尊重され、人としての尊厳が最期まで損なわれることなく暮らすことが可能になる──協会は、そう考えます。
以上